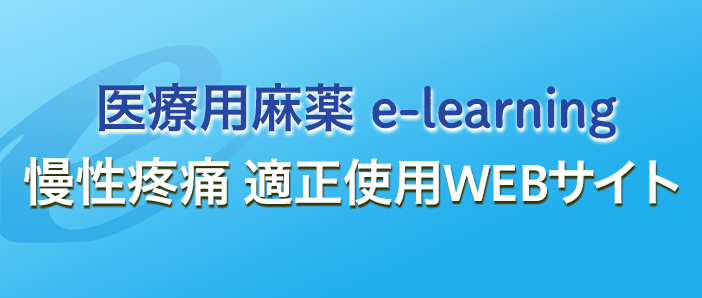5-FU[よくある医薬品Q&A]
用法及び用量(投与法・投与計画)
-
5-FU軟膏の1回の塗布量について知りたい。
PDR(米国医薬品情報集)2024年オンライン版によると、病巣面をカバーできるよう十分な量を塗布するとされています。
なお、一般的な抗腫瘍外用剤の標準的な塗布量は、患部100cm2につき1~2.5gとされています1)。
[参考文献]
1) 斉藤隆三:皮膚病診療 19 (増), 25-34 (1997) [015-998]2025年10月更新
MA-2023-227 -
5-FU軟膏の塗布時の注意について知りたい。
添付文書には以下の記載があります。
<14. 適用上の注意>
14.1 薬剤塗布時の注意
14.1.1 眼には接触させないこと。粘膜周辺に使用する場合には慎重に行うこと。
14.1.2 手で塗布する場合には塗布後直ちに手を洗うこと。
14.1.3 塗布部はなるべく日光にあたらないようにすること。2025年10月更新
MA-2023-227 -
5-FU軟膏のODT療法について知りたい。
5-FU の閉鎖密封療法(Occlusive dressing technique;ODT)とは、5-FU 軟膏を厚めに塗擦した病巣の上に、薄いプラスチックフィルム(サランラップ等)をのせ、周辺を絆創膏で固定する方法で1 日 1 回交換します。一般的に ODT 療法は単純塗擦法よりも効果は優れるとされています。
ODT 療法の特徴は、下記のとおりです。
- 治療薬剤と病巣面の接触が密になる。
- 軟膏が衣服やその他で擦り採られることがないため、無駄なく利用される。
- 汗や皮脂の貯留が表皮の浸軟化に役立ち、薬剤の経皮吸収を増進する。
- 密封することにより、血流の増加、温度の上昇のような有利な変化をもたらす。
- 密封により角質層の水分量が増加し、経表皮性吸収の増大と毛嚢脂腺系の経皮吸収が促進される。
2025年10月更新
MA-2023-227
相互作用
-
5-FUとワルファリンカリウムとの相互作用の機序は?ワルファリンカリウムの投与量の調節方法は?
相互作用の機序は諸説ありますが、5-FUによりワルファリンカリウムの代謝酵素であるCYP2C9の合成が阻害され、ワルファリンカリウムの効果が増強すると推察されているものがあります1,2)。
海外報告によると、併用により早ければ3日後、概ね2~4週間後にプロトロンビン時間の数倍~十数倍の延長が認められています1-5)。また、プロトロンビン時間の延長を認めずに消化管出血を見た報告もあります6)。
併用時にはプロトロンビン時間を密にモニターしながら、ワルファリンカリウムの減量、中止あるいは5-FUの中止を行いますが、調整方法は報告により異なります。Kolesarらは週1回のモニターを推奨しています7)。また、Chlebowskiらは投与開始3日目にワルファリンカリウムの用量調節を行い、用量が安定したら週1回モニターしながら、必要時ワルファリンカリウムの用量を調節しています6)。
Kolesarらによると、5-FUを併用した5例ではワルファリンカリウムを平均44%(18~74%)減量したとしています7)。Carabinoらは併用時にはワルファリンカリウムを20~70%減量する必要があり、また5-FU投与終了後30日以内はプロトロンビン時間を標準域に維持するため、逆にワルファリンカリウムを増量するとしています8)。
[参考文献]
1) Brown MC:Chemotherapy 45 (5), 392-395 (1999) [016-005]
2) Brown MC:Pharmacotherapy 17 (3), 631-633 (1997) [016-006]
3) Aki Z, et al.:Am J Gastroenterol 95 (4), 1093-1094 (2000) [016-007]
4) Wajima T, et al.:Am J Hematol 40 (3), 238 (1992) [012-719]
5) Scarfe MA, et al.:Ann Pharmacother 28 (4), 464-467 (1994) [016-008]
6) Chlebowski RT, et al.:Cancer Res 42 (11), 4827-4830 (1982) [003-954]
7) Kolesar JM, et al.:Pharmacotherapy 19 (12), 1445-1449 (1999) [016-009]
8) Carabino J, et al.:Am J Health Syst Pharm 59 (9), 875 (2002) [016-010]2025年10月更新
MA-2023-227 -
5-FUとフェニトインの相互作用の機序は?フェニトインの投与量の調節方法は?
機序は明確ではありませんが、5-FUによりフェニトインの代謝酵素であるCYP2C9の合成が阻害され、フェニトインの血中濃度が上昇すると推察されているものがあります1,2)。
5-FU誘導体での事例も含めた国内外の報告によると、併用時のフェニトイン中毒(ふらつき、歩行困難、錯乱等)は、概ね併用1~6ヶ月後に認められています1-5)。
併用例の報告によると、フェニトイン血中濃度をモニターしながら、5-FUあるいは5-FU誘導体の適宜中断や減量とフェニトインの減量を行っています1-4)。併用時のフェニトインの用量は報告により異なりますが、併用前の1/3~2/3用量です2,4,5)。フェニトイン中毒発症後、フェニトインをカルバマゼピンに変更し、化学療法を継続している例もあります1)。
[参考文献]
1) Konishi H, et al.:Ann Pharmacother 36 (5), 831-834 (2002) [016-011]
2) Gilbar PJ, et al.:Ann Pharmacother 35 (11), 1367-1370 (2001) [016-012]
3) 原田英昭,他:鳥取医誌 18 (2), 197-199 (1990) [011-131]
4) 原 富英,他:九精神医 38 (1), 36-41 (1992) [009-857]
5) Wakisaka S, et al.:Fukuoka Acta Med 81 (4), 192-196 (1990) [016-013]2025年10月更新
MA-2023-227
副作用・安全性
-
5-FUによる白質脳症は、どのような症状ですか?また、投与中止後に回復しますか?
5-FUによる白質脳症は大脳白質の萎縮、変性を伴う脳症で、初期症状として、歩行時のふらつき、言語障害、めまい、しびれ、傾眠傾向や異常行動、物忘れ等の精神症状の頻度が高くなります。経過中には昏睡~無動無言、昏迷~傾眠、せん妄等の意識障害、健忘、見当識障害、意味不明の言動、構音障害、動作緩慢、眼振、痙攣、振戦等の精神神経症状が見られることが多くなります1)。
投薬中止後も一定期間は進行しますが、その後改善傾向を示します。初発症状の段階で中止した場合には、ほぼ完全に回復することも少なくないとされます。しかし、重篤な後遺症を残すこともあり、重症例では死亡の転帰をとることもあります。対処方法はまず5-FUを中止し、例えば痙攣に対しては抗痙攣薬の投与等を行います1)。
なお、厚生労働省が公開している重篤副作用疾患別対応マニュアル:白質脳症(令和4年2月時点修正)も参考にしてください。
[参考文献]
1) 赤沢修吾ら編、癌化学療法時のemergency、先端医学社、東京、1998、pp123-1442025年10月更新
MA-2023-227 -
重篤な下痢の対応方針について知りたい。
厚生労働省が公開している重篤副作用疾患別対応マニュアル:重度の下痢(令和3年4月改定)には、以下の記載があります。
ASCOのガイドラインの推奨ステートメント1)としては、グレード 1/2の下痢で他の症状がない単純型の症例では保存的治療が選択されるが、グレード3以上の下痢あるいは中等度以上のけいれん・グレード2以上の嘔吐・活力低下・発熱・敗血症・白血球減少・血便・脱水などの症状を伴うケースは、合併症例として、より綿密な観察と治療を要する。
[参考文献]
1) Benson AB, et al.:J Clin Oncol 22 (14), 2918-2926 (2004) [027-210]2025年10月更新
MA-2023-227 -
5-FUによる手足症候群とはどのようなものですか?
5-FUによる手足症候群は手・足・爪を好発部位とし、軽度のものは紅斑、色素沈着に終わりますが、高度なものは疼痛性に発赤腫脹し、知覚過敏、歩行困難、物がつかめないなどの症状を訴えて水疱、びらんを形成します。やがて手掌足蹠は角化、落屑が著明になって亀裂を生ずるようになり、爪は著明な変形を残すこともあります。発現頻度は5-FUの投与方法に関与し、長時間の持続点滴法による発現率が高いとされます1)。また高い血中濃度が持続すると出現しやすいようですが、短期間投与で出ることもあり個人差も大きいとされます1)。
対策として軽度な皮膚変化では投与続行は可能ですが、剥脱性皮膚炎、疼痛を伴うようになれば一時的に中止もしくは減量します。局所はステロイド剤外用で2~3週にて軽快することが多いですが、ステロイド内服も有用です。またピリドキシン(ビタミンB6)投与が有用とする報告もあります2)。
[参考文献]
1) Lokich JJ, et al. :Ann Intern Med 101, 798-800 (1984) [010-346]
2) Fabian CJ, et al. :Invest N Drugs 8, 57-63 (1990) [010-179]2025年10月更新
MA-2023-227