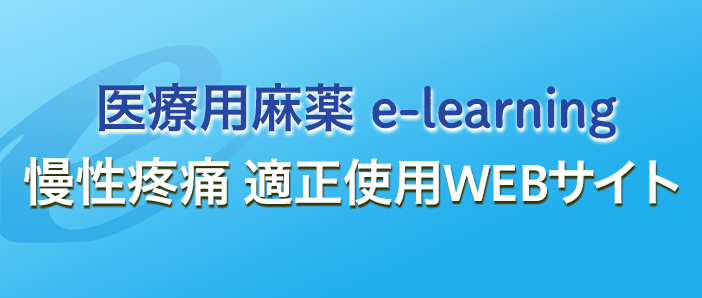ロイナーゼ[よくある医薬品Q&A]
副作用・安全性
-
ロイナーゼ皮内反応試験の推奨実施時期と溶液の調整方法は?
ロイナーゼはショックを起こすおそれがあるため、ロイナーゼ投与に先立って皮内反応試験を実施することが勧められます。特に1クール終了後、休薬期間をおいて再投与する時に起こりやすいので再投与開始時には、皮内反応試験を実施することが勧められます。
添付文書には、具体的な皮内反応試験方法の一例として以下の記載があります。
<14. 適用上の注意>
14.2 薬剤投与前の注意
14.2.1 皮内反応試験
本剤5000K単位を日局注射用水2mLで溶解後、日局生理食塩液にて全量5mLとする。このうち0.1mLを注射筒で分取し、日局生理食塩液で全量1mLとした後、この0.1mLを皮内注射する(投与量:10K単位)4)。皮内注射後15~30分間異常がないことを確認すること。[8.4参照]
<備考> 24th Ed. USPDI(R)(米国薬局方医薬品情報集)によると、皮内反応試験実施時期は初回投与及び投与間隔が1週間以上あいた時に実施することが薦められている、と記載されています。
【引用文献】
4)土屋純ほか:臨床検査. 1988; 32: 205-2082025年10月更新
MA-2023-203 -
ロイナーゼ投与によるショックの対策は?
本剤は大腸菌由来のタンパク製剤であり、生体にとって異種タンパクであるので、抗原抗体反応により過敏反応を来たす可能性があります。ショック症状の発症は投与直後から30分以内に起こることが多く、特に維持療法中あるいは再発後の再寛解導入時での発現が高いと報告されています1)。
ショックは初期の治療により予後が左右されることが多いので、初期症状(血圧低下、悪感、発熱、嘔吐など)のチェックが重要で、発症後すぐに対処することが重要であり、ロイナーゼの投与を即時に中止します。アレルギー症状に対しては、ステロイド剤・抗ヒスタミン剤の投与等を行い、アナフィラキシーショックに対しては、血圧維持と気道確保を基本としたショックへの対応(酸素吸入、エピネフリンの投与、電解質輸液用液の投与等)を行います。
また、筋肉内投与は静脈内投与に比べ、アナフィラキシーの発現が低いことが報告されています2)。
なお、ロイナーゼ投与前には皮内反応試験を行い、異常がないことを確認することが推奨されます。
添付文書には以下の記載があります。
11.1 重大な副作用
11.1.1 ショック、アナフィラキシー(いずれも頻度不明)
じん麻疹、血管浮腫、悪寒、嘔吐、呼吸困難、意識混濁、痙攣、血圧低下等の症状があらわれた場合には直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。[8.4参照]
[参考文献]
1) Capizzi RL, et al. : Cancer Medicine, 3rd edition, 796-805 (1993) [012-029]
2) 服部拓哉,他 : 小児科診療 47(6), 928-934 (1984) [004-511]2025年10月更新
MA-2023-203 -
ロイナーゼによる高アンモニア血症の発症メカニズム、頻度、対処法は?
ロイナーゼはアスパラギンおよびグルタミンを分解してアンモニアを発生させるため、血中アンモニア濃度が高値となります。アンモニアは神経毒性を有するため、嘔吐、傾眠傾向、昏睡、意識障害等の中枢神経症状を来たします。
発現頻度は、承認時までの調査および市販後の副作用調査(~S.51.5.1)で12.5%(12/96)です。ただし、臨床症状を伴わない血清アンモニア値の上昇は17.5~26.3%で発現しています1,2)。
血中アンモニア値は、ロイナーゼ投与開始1週間前後(3~10日後)でピーク値を示し、その後、ロイナーゼ投与中でもアンモニア値は次第に低下する傾向があります。アンモニア値の持続的な上昇がみられない場合には臨床的に問題ないとする報告があります3,4)。
血中アンモニア値のピークが400μg/dL以下の場合、中枢神経障害を思わせる自覚症状や理学所見は認められず、アンモニア値はロイナーゼ終了後数日で全例正常化したとの報告があります4)。
重篤な急性脳症の疑いがある場合は、交換輸血あるいは血漿交換を考慮します3)。またタンパク摂取の制限や安息香酸ナトリウム、アルギニン、カナマイシン、ラクツロース、アルギメート等の投与が行われることがあります1,3,5)。
投与後は注意深い経過観察と血中アンモニア値のモニタリングを行うことが推奨されます。
添付文書には以下の記載があります。
<11. 副作用>
11.1 重大な副作用
11.1.4 意識障害を伴う高アンモニア血症(頻度不明)[9.3参照]
[参考文献]
1) 児玉順三,他 : 成人病の研究 1(1), 77-84 (1972) [004-590]
2) 久川浩章,他 : 臨床血液 31(8), 1409 (1990) [015-318]
3) 石田也寸志,他 : 日児誌 95(6), 1440-1445 (1991) [011-022]
4) 石田也寸志,他 : 臨床血液 30(9), 1503 (1989) [015-320]
5) 和田義郎,他 : 小児科診療 58(S), 568-570 (1995) [015-321]2025年10月更新
MA-2023-203 -
ロイナーゼによる血糖上昇や糖尿病のメカニズムは?
ロイナーゼによる耐糖能異常のメカニズムの詳細は不明ですが、ロイナーゼのタンパク合成阻害によるインスリン合成抑制、インスリンレセプターの減少等の他、膵臓への直接障害により膵β細胞のインスリン合成を阻害する可能性が考えられています1)。
[参考文献]
1) 土肥潤子,他 : 日本小児科学会雑誌 91(7), 1683 (1987) [007-800]2025年10月更新
MA-2023-203 -
ロイナーゼによる血液凝固障害発症のメカニズムは?
ロイナーゼ(一般名:L-アスパラギナーゼ)による血液凝固障害としては、血栓症・梗塞と出血のいずれも報告がされていますが、フィブリノーゲンが著しく低値でも梗塞を発症した例が多く報告されており1)、現在ではL-アスパラギナーゼによる血液凝固障害の大半は血栓症・梗塞であり、出血の多くは梗塞に伴う二次的な症状と考えられています。
発症のメカニズムは、L-アスパラギナーゼの薬理作用であるタンパク合成阻害により肝臓で生成される凝固線溶系因子の合成阻害が起こり、その結果、何らかの要因により各因子のバランスが崩れて発現すると推定されています。その要因の一つとしてアンチトロンビンやプラスミノーゲンに比べフィブリノーゲンが早く回復するため凝固亢進状態となるとの報告2)、さらにアンチトロンビンの血液凝固障害に対する影響を重視する報告3)があります。
また凝固線溶系因子の変動を検討した報告4)では、L-アスパラギナーゼ単独投与により21種類の因子のうち第VII因子を除くすべての因子が減少し、とくにアンチトロンビンなどが著明に低下しました。L-アスパラギナーゼ、ステロイドを含む多剤併用療法では、ステロイドの凝固系因子の増加作用により症例の凝固系因子の減少は軽微でした。なお、ほとんどの症例で凝固線溶系因子の低下が認められますが、実際に血液凝固障害を起こす症例は少数です。これは各因子の低下が一過性であることが多いことと、大部分の因子がバランスを保って低下することが原因と考えられています5)。
[参考文献]
1) Priest JR, et al. : Cancer 46(7), 1548-1554 (1980) [015-437]
2) Kucuk O, et al. : Cancer 55(4), 702-706 (1985) [005-567]
3) 船曳哲典,他 : 化学療法の領域 16(10), 1727-1732 (2000) [015-438]
4) Mitchell LG, et al. : Am J Pediatr Hematol Oncol 16(2), 120-126 (1994) [015-439]
5) 吉岡 章,他 : 日本小児科学会雑誌 90(12), 2625-2633 (1986) [008-162]2025年10月更新
MA-2023-203 -
ロイナーゼによる血液凝固障害の予防法、対処法は?
ロイナーゼ(一般名:L-アスパラギナーゼ)による血液凝固障害の予防法は確立されていないので、早期発見がポイントとなります。そのため、投与中はフィブリノーゲン、プラスミノーゲン、アンチトロンビン、プロテインC等の検査を頻回に行い、十分観察する必要があります。なお、ほとんどの症例で凝固線溶系因子の低下が認められるので、血液凝固障害の可能性を念頭におく必要があります。 脳、肺、四肢等の出血傾向や血栓が疑われた場合、直ちに投与を中止し、凝固線溶系因子の測定と同時に、出血や血栓を確認する為にCTやMRIが有用とされます1)。
厚生労働省医薬・生活衛生局から出ている「血液製剤の使用指針 平成30年3月改定版」では、アスパラギナーゼ投与に関連して、凝固因子の減少、抗凝固因子や線溶因子の産生低下を同時に 補給するためには新鮮凍結血漿(FFP)を用い、アンチトロンビンの補充を必要とする場合はアンチトロンビン製剤を使用するとされています。
また文献では、フィブリノーゲン100mg/dL以下、アンチトロンビン80%以下を目安にFFP、アンチトロンビン製剤を投与することを推奨する報告があります2)。しかし一方で、FFP投与後に血栓症を発現した報告3)やアンチトロンビン製剤を投与することで血栓を予防する傾向を示したとの報告4)もあります。
さらに、血栓性素因を持つ患者や中心静脈カテーテル留置中の患者では、血栓症の発症頻度が高くなるので、ヘパリン投与などの予防処置が必要と考えられます5)。
[参考文献]
1) Feinberg WM, et al. : Neurology 38(1), 127-133 (1988) [008-552]
2) Muntean W: J Pediatr 102(3), 483-484 (1983) [003-306]
3) Ishii H, et al. : Am J Hematol 41(4), 295-296 (1992) [015-440]
4) Mitchell L, et al.:Thromb Haemost, 90(2), 235-244 (2003) [017-577]
5) 船曳哲典,他 : 化学療法の領域 16(10), 1727-1732 (2000) [015-438]
2025年10月更新
MA-2023-203