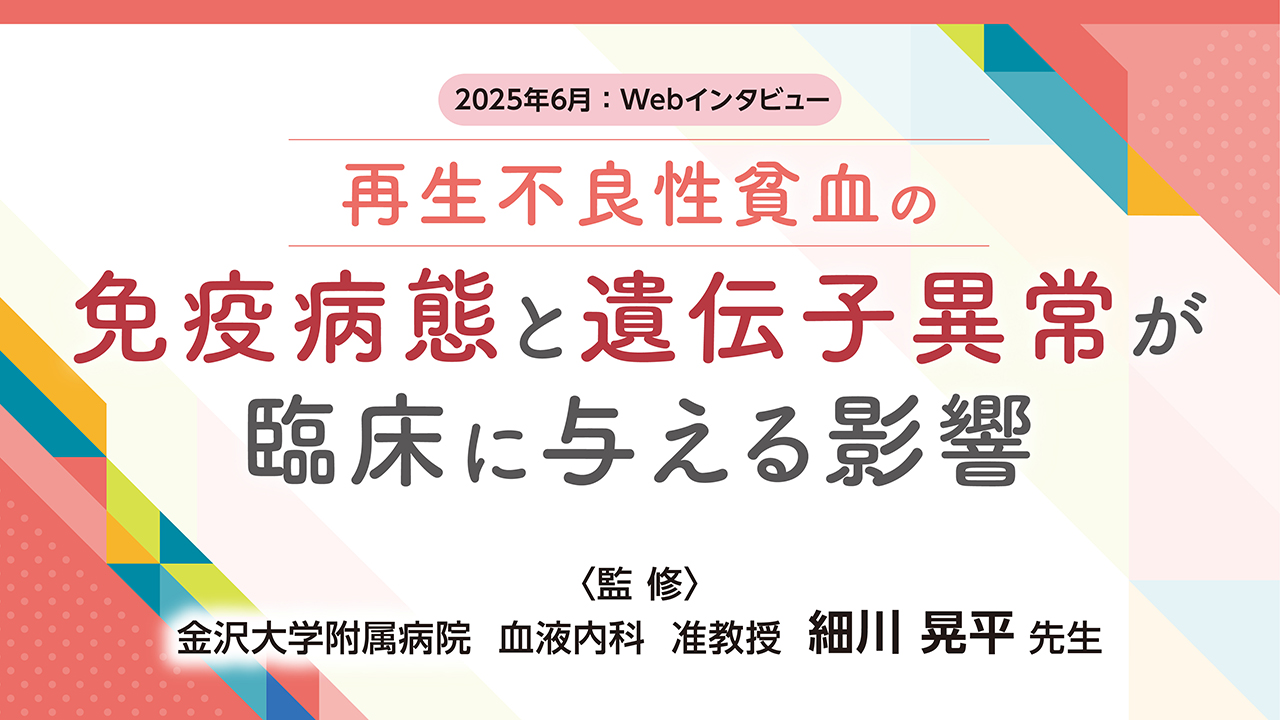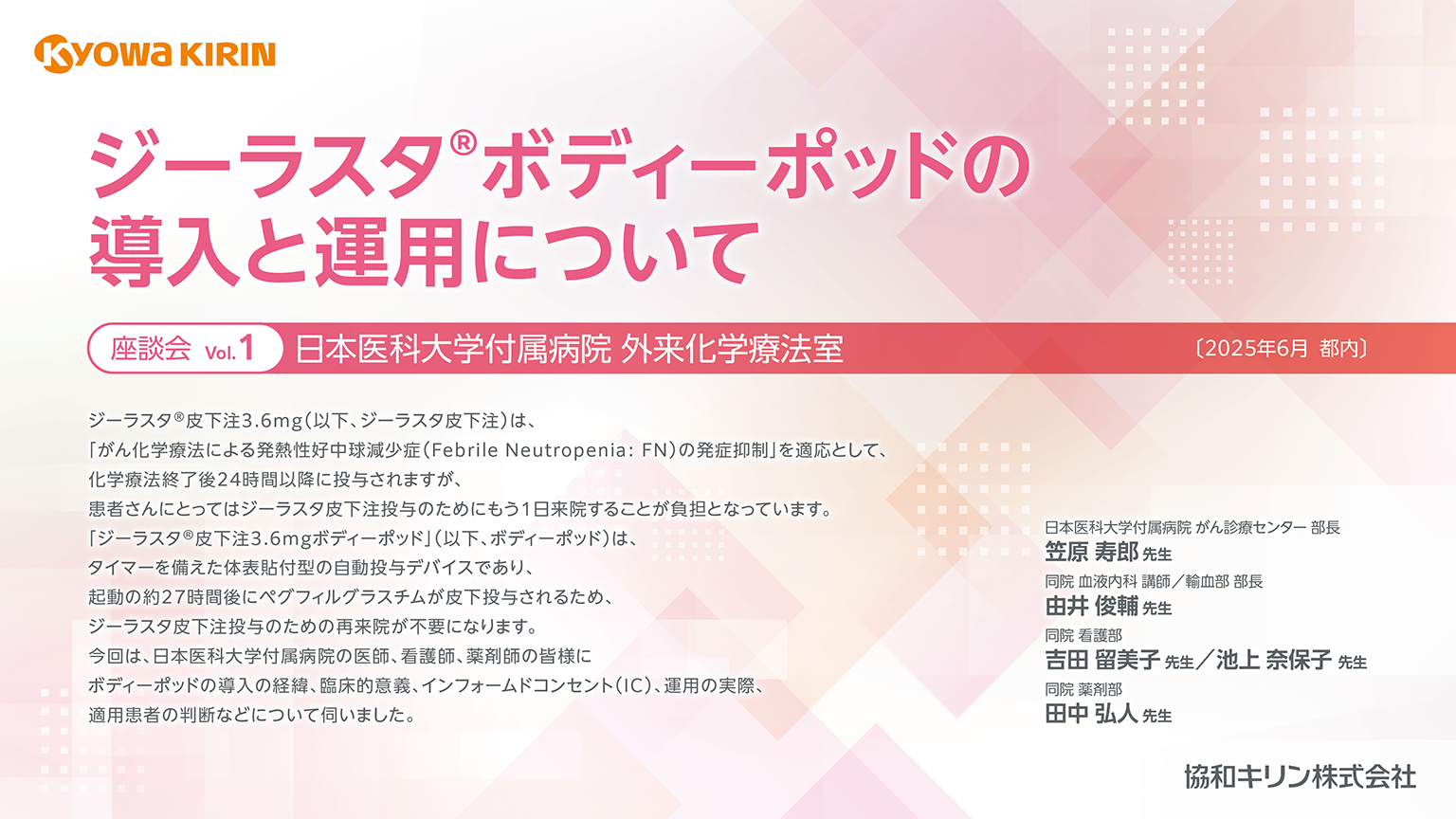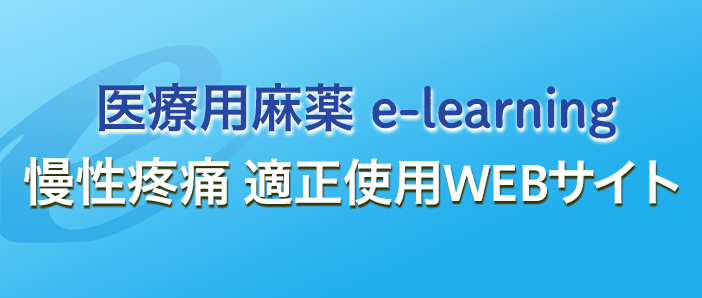医療法人徳洲会 東京西徳洲会病院
[外来化学療法 現場ルポ]
2025年4月21日公開/2025年4月作成

- ●開設:2005年
- ●所在地:東京都昭島市松原町3-1-1
多職種によるチーム医療を構築し
がん患者の治療と生活を支える
東京西徳洲会病院は、徳洲会グループが初めて東京都内に開設した総合病院で北多摩西部地区を中心に約65万人の診療圏をカバーしている。がん医療では、乳がんと前立腺がんで東京都がん診療連携協力病院の指定を受けており、「包括的がん診療センター」を開設し、世界水準のがん治療を提供。がん化学療法看護認定看護師が中心となってチーム医療を構築し、安全で効果的ながん薬物療法に取り組んでいる。
1. 病院の特徴
地域の総合病院の役割を担いつつ
乳がんを中心にがん医療に取り組む

佐藤 一彦 名誉院長/包括的がん診療センター長/乳腺腫瘍センター長
東京西徳洲会病院は、徳洲会グループが初めて東京都内に開いた総合病院。2005年9月の開院以来、北多摩西部地区を中心に約65万人の診療圏をカバーし、「生命を安心して預けられる病院・健康と生活を守る病院」という徳洲会の理念のもと、職員が一丸となって診療を提供している。
なかでも強固な診療体制を築き上げた救急医療では、年中無休24時間体制で患者を受け入れており、患者が搬送されてくる地域は埼玉県西部、山梨県上野原方面、神奈川県相模原方面に及ぶ。また、災害拠点連携病院の指定を受けているため、大規模災害が発生した際には北多摩西部地区の最西端の砦としての役割も担う。
がん医療においては、乳がんと前立腺がんで東京都がん診療連携協力病院の指定を受けている。「包括的がん診療センター」を開設し、世界水準のがん治療の提供を目指して診療体制を整備してきた。
包括的がん診療センターでは、外科療法、放射線療法、薬物療法などを効果的に組み合わせて根治を目指す集学的治療を基本に診療を行っている。たとえ治せない状況であっても、がんとの共存を視野に入れ、積極的に緩和ケアに取り組み、患者と家族の生活を支えている。
「より適切な集学的治療や緩和ケアを行うために2名の乳腺腫瘍医(常勤)が中心となり、関連する診療科医師および医療スタッフとともに治療方針などを検討する『Tumor board』を毎週1回、定期的に開催しています」と包括的がん診療センター長を務める佐藤一彦名誉院長は説明する。
包括的がん診療センターに併設する乳腺腫瘍センターは、乳がんをはじめとする乳腺疾患に特化した診療を行っている。なかでも乳房を残したい人のために「乳房温存手術」に積極的に取り組み、放射線医学センターや化学療法センターとも緊密に連携しながら世界標準の治療を提供している。「例えば、乳房温存手術後の全乳房照射に代わる手段として期待されている乳房部分照射は治療の選択肢として重要なため、いち早く導入しました。今ではいくつかの大規模臨床試験で有用性が示されており、日本での普及が期待されています」(佐藤名誉院長)。
当センターではいくつかの方法のうち、小線源を活用した IOCI(Intraoperative Open-Cavity Implant)法による乳房部分照射を行っており、手術時に乳房内にアプリケーターを留置し、乳房内から局所照射を行う。一般的に、放射線照射は術後3~6週間要するが、IOCIの場合、初回手術の入院の際に実施でき、しかも4~5日で終了するため、患者の心身の負担だけでなく、経済的負担もかなり軽減される。同センターで実施される乳がん小線源療法は、国内はもとよりアジアでも1、2を争う症例数を誇り、2024年度中には1,000例に達した。

乳腺腫瘍センターと包括的がん診療センターは隣接し、がん医療を専門とする看護師、薬剤師が配置されている

毎週火曜の夕方に開催される「Tumor board」。医師のほか、看護師、薬剤師、管理栄養士、理学療法士など治療に関わる多職種が参加。化学療法を開始する新規患者は全員Tumor boardで治療方針の検討が行われる
2. 化学療法センターの特徴
チーム医療による緊密な連携により
外来・入院を問わず化学療法に対応、
包括的がん診療センターには抗がん剤治療部門として「化学療法センター」が設置され、外来・入院を問わず、院内におけるすべての化学療法を実施している。17床(リクライニングチェア10床、ベッド7床)を有する化学療法センターの稼働日は月・水・金の週3日で、これは開院以来、変わっていない。治療実績は年間約3,000件、月平均では約250件。日にすると25件前後となり、このうち初回治療者は多いときで3~4人、平均的には1~2人である。血液がん、脳腫瘍、小児がんを除く、すべてのがん種に対応するが、乳がんが約半数を占め、次いで消化器がん(3割)が続く。患者の平均年齢は比較的若い世代が多い。
化学療法センターでは約8年前から予約システムを導入し、どの診療科からも診療枠が可視化された状況のもとで運営されており、ベッドコントロールなどのマネジメントは平本亜希子がん化学療法看護認定看護師(以下、認定看護師)が中心となって調整している。
化学療法センターには看護師5名、薬剤師6名、受付事務1名が配属されているが、専任者は看護師と薬剤師が1名ずつで、そのほかのスタッフはいずれも外来業務・院内業務との兼任である。限られたマンパワーで、化学療法を安全・安心かつ効率的に実施するためには"チーム医療による緊密な連携"が欠かせず、化学療法センターではその強化に取り組んできた。
その成果の一つが看護師と薬剤師による朝のミーティングである。
前治療から当日までの緊急受診の有無の確認など患者の情報を共有し、注意点などを確認する。薬剤師は調製業務を行いながら、採血結果や医師カルテの確認を行っている。その中で、カルテ内容や採血結果で気になる点がある際は、看護師とその情報を共有し、患者の状態を看護師が実際に確認することもある。
一方で、患者の状態が血液検査などのデータだけでは反映されにくいこともあるため、平本認定看護師は患者の状態を問診票と併せて観察することも重視している。受け持ちスタッフなどから、「調子が悪そう」などの情報があれば、平本認定看護師が直接、バイタルサインや体調を確認し、安全な化学療法が行えるよう取り組んでいる。
近年、免疫チェックポイント阻害薬などの高額な薬剤を使用することも多く、調製後の中止を避けるために、調製前に患者の体調確認を行っている。

平本亜希子 がん化学療法看護認定看護師


化学療法センター。乳がんを中心に比較的若い世代の患者が多いことからベッドよりもリクライニングチェアを多めに配置している
3. 看護師の役割
看護師が患者の困り事を拾い上げ、
多職種と連携して療養・生活支援へ
化学療法センターでは、看護師は受け持ち制ではないが、点滴を開始する看護師が問診票を確認し、患者の体調を含め、自宅での様子を聞き取っている。
「患者さん全員の電子カルテを前日に確認し、療養・生活サポートが必要な人にはフラグを立てています。その内容を朝ミーティングでスタッフと共有し、ベッドサイドでの問診の際に、療養・生活面での課題を詳しく聞いてもらうこともあります」(平本認定看護師)。
こうして看護師が患者の困っている問題を拾い上げ、収集してきた情報をもとに平本認定看護師がハブとなり、多職種(医師、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、メディカルソーシャルワーカー、歯科医、訪問看護師、疼痛緩和チームなど)と連携し、さまざまな療養・生活サポートが受けられる仕組みが出来上がっている。「多職種と連携構築するうえで顔の見える関係とコミュニケーションを取ることがとても大切だと考えています。それは患者さんの安心・安全につながり医療スタッフとの信頼につながると考えています」(平本認定看護師)。
また、複雑なレジメンが増える中、看護現場における安全性を高める工夫として薬剤師と連携した勉強会の開催に力を入れている。例えば、新薬の採用の際は、その薬剤を使用するとき、何が問題になるのかを平本認定看護師と薬剤師が検討し、看護師にも意見を聞いたうえで勉強会での指導内容を決めている。
そして、患者に初めて新薬を投与するときは平本認定看護師が対応し、実働を通して再度問題点を洗い出して投与手順に反映し、指導内容のブラッシュアップを図る。さらに、看護師が初めて投与する際には平本認定看護師がマンツーマンで付き添い、サポートする。「外来・病棟業務との兼務で活動する看護師が手順を間違えることなく、安心・安全に化学療法の業務に取り組んでもらえるよう最も神経を使っている部分です」(平本認定看護師)。
また、看護部では2016年からIVナース(院内IV認定看護師)の育成に取り組んでおり、平本認定看護師は2021年から責任者を務めている。教育内容を3段階に分け、1段階に1年かけてeラーニングによる研修を行ったうえで履修テストを実施し、合格者のみ次の段階に進める教育システムで、IVナースと認定されるまで最短でも3年かかる。そのため、全ナース(389名)を対象としたものだが、IVナースに認定されている看護師は22名だ(2024年現在)。「レベル3は抗がん剤治療に携わる看護師に限定したカリキュラムです。将来的にはIVナースを化学療法センターに配属できるよう各病棟・外来の所属長の協力を得ながら、精力的に育成に取り組んでいます」(平本認定看護師)。
一方で、化学療法センターの看護師は子育て中のスタッフが多いため、定時に帰宅できるよう業務の効率化にも工夫を凝らし、働きやすい職場環境の整備に努めている。「例えば、抗がん剤の投与時間が長い患者さんは早く治療を始められるように予約システムの画面に★マークを付け、主治医に優先的に診察してもらっています。診察を補助する外来看護師とも★マークの意味を共有し、主治医が★マークを見落としても外来看護師が診察の順番をコントロールできる仕組みにしています」(平本認定看護師)。
4. 薬剤師の役割
地域の薬局との「がん薬薬連携」にも注力
勉強会を通して保険薬局の活動をサポート
薬剤部では、バーコード認証用のハンディ端末や最終鑑査システムを導入し、調剤ミス防止など医療安全の取り組みを推進しながら、薬剤師が医師や看護師と協働し、安全で効果的な薬物療法に従事する体制づくりに注力してきた。前述したように化学療法センターでは6名の薬剤師が主に監査・調製の業務を担当する。「がん薬物療法認定薬剤師」の資格取得を目指して研修中の堀越俊彦薬剤師は専任で配属されており、ほかの5人は化学療法センターを希望する4人の薬剤師に加えて2年目の薬剤師がローテーションで担当している。
「平本認定看護師同様、私も前日までに翌日治療を行う患者さん全員の診療情報を確認します。カルテの記載内容や検査値、病状によってはCTなどの画像にも目を通したうえで朝ミーティングに臨みます」(堀越薬剤師)。化学療法センターのスタッフステーションでは平本認定看護師と向かい合わせのデスクでカルテ入力の作業をすることも多く、顔を合わせたときにそれぞれが気になっている患者情報を共有し、その場で対策を話し合うことが日常となっている。
また、初回投与の患者にはもれなく薬剤師面談を実施している。「患者さんの背景(家族構成、生活環境など)を聞き取りながら副作用を中心に1時間ほどかけて薬物療法の説明をします。この際に必ず伝えるようにしているのは"副作用がでたときは我慢せず言ってください"ということ。副作用には検査でわかるものとわからないものがあることを患者さんに認識してもらったうえで、検査だけではわからない副作用について早期に対応するためには自己申告が不可欠であることを理解してもらいます。同時に看護師もベッドサイドでの声かけを積極的に行っているため、連携して患者さんが医療者につらさを訴えやすい環境を整えています」(堀越薬剤師)。
一方、地域の保険薬局との「がん薬薬連携」にも注力している。お薬手帳を通して副作用情報(発現状況、グレード評価など)を提供するほか、薬剤部のホームページでレジメンを公開している。また、保険薬局が取り組んでいる「テレフォンフォローアップ」の活動を支援しており、堀越薬剤師は次のように説明する。「2020年から保険薬局を対象とした定期的な勉強会も開催しています。集合研修では参加者に、摸擬症例の副作用を予測したうえでテレフォンフォローアップのタイミングについて計画表を作成してもらったり、副作用のグレード評価したうえで対処法についてグループディスカッションしたりするなど症例検討を中心とした実践的な内容となっています」。
2025年の定期勉強会では、グループディスカッションの際に薬剤部の若手薬剤師にも参加してもらい、保険薬局薬剤師と合同で副作用の治療計画を立案することを企画している。このような協働トレーニングを繰り返すことによって"顔の見える関係"を築くこと、そして薬剤部と保険薬局が共同薬剤管理を行っていく素地を醸成する効果も期待する。
「がん薬物療法の発展により(がん治療は)患者さんがそれぞれの日常生活を行いながら継続するものとなっており、これから保険薬局との連携はますます重要になってきます。当院だけでなく、北多摩薬剤師会でも勉強会をベースにしたがん薬薬連携小委員会を新設する動きがあり、その体制づくりや運営にも携わっています。地域の保険薬局のニーズを丁寧に拾い上げ、勉強会に積極的に参加していただくことで、がん薬物療法に関わる薬局薬剤師を一人でも多く増やすことを目指しています」(堀越薬剤師)。

堀越 俊彦 薬剤師
5. 展望と課題
診療の質をよりレベルアップするために
看護師や薬剤師の学術活動に期待
化学療法センターは、看護師も薬剤師も限られた人数の中、日々の薬物療法を遂行しなければならない環境に置かれている。そのため知恵と工夫を凝らし、専門的な知識を持つスタッフが中心となってチーム医療を発展させてきた。「病院の規模が、多職種によるチーム医療を円滑に進めるうえでちょうどよく、院内連携はきわめてうまくいっていると評価しています」(佐藤名誉院長)。
そのうえで今後の課題として平本認定看護師はタスクシフトの推進を挙げる。「各職種の専門性を生かすためにも患者さんがいつでも気軽に立ち寄れる相談窓口の設置が重要です。また、薬剤師外来も近々立ち上げる計画があり、その検討が始まっています。これらの活動を行っていくうえでマンパワーの確保が必須で、看護師と薬剤師を中心に職種の役割をもう一度整理し、タスクシフトを推進していくことが欠かせません」(平本認定看護師)。
佐藤名誉院長はチーム医療をいま以上に充実させ、がんに立ち向かう患者をしっかり支えていくには医師だけでなく各職種が専門性を究めることが必須だと言う。それには自分たちの活動を何らかの形でレビューすることが肝心で、その一つの指標として医療スタッフが学術活動に取り組むことを期待する。「私たちはがん薬物療法を含め、がん医療を実践する際にエビデンスを何よりも重視しています。エビデンスを吸収するには他人の論文を批判的に吟味することが必要ですが、自分でもアウトカムを出すような取り組み、つまり学術活動を行わなければ批判的吟味を行うことは難しいのです。最終的には患者さんのよりよいケアにつながるため、看護師や薬剤師にはぜひ頑張ってほしい」と佐藤名誉院長はエールを送る。
地域の総合病院であっても世界水準のがん治療の提供を――。東京西徳洲会病院包括的がん診療センターは、多職種が緊密に連携するチーム医療を強みとし、さらなる高みを目指して前進する。
KKC-2025-00234-1
外来化学療法 現場ルポ
-
2025年4月21日公開/2025年4月作成
-
2024年12月19日公開/2024年12月作成
-
2024年12月9日公開/2024年12月作成
-
2024年12月5日公開/2024年12月作成
-
2024年11月19日公開/2024年11月作成
-
2024年11月18日公開/2024年11月作成
-
2024年2月26日公開/2024年2月作成
-
2024年1月30日公開/2024年1月作成
-
2024年1月29日公開/2024年1月作成
-
2023年12月20日公開/2023年12月作成
-
2023年12月7日公開/2023年12月作成
-
2023年12月5日公開/2023年12月作成