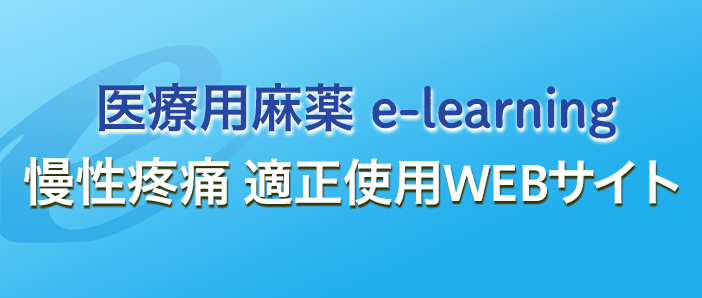愛知医科大学病院
[パーキンソン病 med.front]
2023年2月21日公開/2023年2月作成
多様なパーキンソン病患者をワンストップで治療
デバイス治療を推進し患者のQOLをアップ
愛知医科大学病院は、22の診療科と900床の病床を擁する基幹病院である。神経内科領域では名古屋市を含む愛知県東部地域の診療拠点として、神経疾患全般を網羅して幅広い診療を行っている。2020年には、増え続けるパーキンソン病患者の治療をワンストップで行うことを目的に、「パーキンソン病総合治療センター」を開設した。神経内科医と脳神経外科医、その他の専門医や多職種が連携し、患者の病態に合わせて最新かつ良質の医療を提供。特にDBS、経腸療法などのデバイス治療で成果を上げている。

- ●病院長:道勇 学 先生

- ●開設:1974年
- ●所在地:愛知県長久手市岩作雁又1-1
目次
-
パーキンソン病総合治療センターの概要
DBS、経腸療法などデバイス治療の核
他科の医師、多職種と連携し高度な医療を提供 -
検査入院
外来での診断が困難なケースを詳細に検査し評価
デバイス治療の導入も入院で慎重に検討 -
DBS
脳神経外科医3名による手術を神経内科医2名が補助
術前術後は看護師がきめ細かく患者をサポート -
多職種連携による経腸療法
薬剤師を中心に多職種が連携
1週間の体験入院を経て導入し外来でフォロー -
調整のための入院
薬剤師、看護師、リハビリスタッフの目を活かし
薬剤の量や投与間隔、刺激の強さを適切に調整 -
リハビリテーション
病棟リハ室を活用して入院患者の評価と訓練
近隣病院の協力で入院リハビリも提供 -
今後の課題・展望
人材育成、患者への啓発、広報活動などを充実
"パーキンソン病なら愛知医大"と言われる存在に
1. パーキンソン病総合治療センターの概要
DBS、経腸療法などデバイス治療の核
他科の医師、多職種と連携し高度な医療を提供

斎木 英資 パーキンソン病 総合治療センター 教授
愛知医科大学病院は1974年の開院以来、基幹病院として地域医療を牽引してきた。開設40周年にあたる2014年には新病院を開院し、それまで以上に高度で先進的な医療を提供できる体制を構築している。
「パーキンソン病総合治療センター」の開設は2020年4月。開設の目的は、増え続けるパーキンソン病患者一人ひとりに、より先進的で良質な医療を提供することだ。特に近年、注目度が高まっているDBS(脳深部刺激療法)、経腸療法といったデバイス治療を行うことを大きな使命としている。そのために招聘されたのが、2020年7月より同センター部長を務める斎木英資教授である。
「私は神経内科専門医で、特にパーキンソン病をはじめ運動障害疾患を専門分野としています。薬物療法や運動療法を行うのと併行してDBSの前身ともいえる定位脳手術に、当時の勤務先の脳外科部長とともに着手したのは研修医の頃でした。1994年にはじめてDBSが論文化されてからはDBSも行うようになり、2000年に保険適用されて以降は継続的にDBSに取り組んでいます。こうした実績を評価していただき、当院に赴任することになりました」と斎木教授。道勇学・愛知医科大学病院長と以前から交流があり、折りに触れて着任を打診されていたことも背景にあったと振り返る。
同センター所属のスタッフは斎木教授ほか、脳神経外科専門医の名倉崇弘講師、神経内科専門医の田口宗太郎医師の3名。パーキンソン病の一般的な治療は神経内科主体で行い、手術の適用を検討するときや手術適用が決まってからは同センターが主体となり、他科の協力を得ながら治療を進める仕組みだ。
「DBSの適応の検討では認知機能を詳細に調べる必要があり、精神科の医師に協力していただいています。また、経腸療法を行うときには、消化器内科の医師にサポートしていただくというように、当センターを核として他の診療科との連携を広げています。さらに、実績を重ねることで医師以外の職種にも興味を持っていただき、積極的にかかわっていただくことで、当院のパーキンソン病治療の底上げを図ることも私たちの使命です」と、斎木教授がパーキンソン病総合治療センターの役割を語る。
同センターの活動は斎木教授の就任を機ににわかに活発化し、DBSや経腸療法が積極的に行われている。また、パーキンソン病総合治療センターという大きな"受け皿"ができたことで、斎木教授の就任前後を比べると、パーキンソン病およびパーキンソン病関連疾患による入院患者は約2倍に増えている。

名倉 崇弘 パーキンソン病総合治療センター 講師

田口 宗太郎 パーキンソン病総合治療センター 医師
2. 検査入院
外来での診断が困難なケースを詳細に検査し評価
デバイス治療の導入も入院で慎重に検討
パーキンソン病が疑われる患者、あるいはすでにパーキンソン病と診断されているものの治療法などで困っている患者などが同院にアクセスする最初の窓口は、神経内科の一般外来、あるいは斎木教授と田口医師が担当する専門外来であるパーキンソン病外来である。
「手が震える、歩きにくいといった症状のある方が、地域の医療機関から紹介されてくるケースが多いです。神経内科では毎日、20名の医師の曜日担当制で、外来診療室を3〜5室使って診療を行っていますので、まずはそこに来ていただきます」と田口医師。ここで症状や経過からパーキンソン病であると診断できる場合は薬物療法を開始する。
外来ではなかなか診断がつかない場合は検査入院となる。検査入院の平均入院期間は約2週間。この間には、画像検査を含めて複数の検査を組み合わせて行ったり、薬の反応性を調べたりする。十分な検討を重ねたうえでパーキンソン病であることが見えてきたら薬の投与を開始する。
検査入院には、このようにパーキンソン病の診断を主な目的とする場合のほかに、デバイス治療を導入するかどうかの判断を主な目的とする場合がある。後者の場合は、はじめに外来で1時間程度の枠を取って経過などを聞き、デバイス治療によって効果が出るかどうか、デバイス治療をしないほうが良い要素はないかなどを見きわめる。
「たとえばDBSの場合なら、薬を1日5回投与しても症状が十分コントロールできない、認知機能の低下が見られない、といった条件を満たした場合にさらにくわしい説明を行い、患者さんが希望すれば入院による検査を実施します。DBS検討のために患者さんが入院されたら、その時点から関係者が情報を共有します。DBSの効果が期待でき、リスクも少ないと確認できた場合は、そのことを患者さんに説明し、導入するかどうかの意思決定を支援します。治療効果と患者さんの利益は必ずしもイコールではありません。最終的には治療を受けることがご自分の人生の役にたつかどうかをよく考え、決めてもらうようにしています」と、DBS導入までの流れを、斎木教授が紹介する。
3. DBS
脳神経外科医3名による手術を神経内科医2名が補助
術前術後は看護師がきめ細かく患者をサポート
最終的に患者がDBSの導入を希望したら、パーキンソン病総合治療センターを中心に手術に向けて具体的に動き出す。名倉講師から患者に対し、手術内容やDBSで用いる各種機器の細かな特徴などについて説明を行う。手術日程についてはあらかじめ関係職種の都合を擦り合わせておき、患者の了解が得られれば決定となる。
「入院は手術の前日なので、準備するものや注意事項などは、外来診療時にあらかじめ外来担当看護師からお伝えしておきます。入院後は、集中治療室の看護師や手術室の看護師が術前訪問のかたちで面談を行います。さらに私たち病棟看護師が、手術を担当する医師や麻酔科医の指示にしたがって患者さんの準備を整えます」とDBS手術における看護師の役割を紹介するのは、神経内科病棟の小出愛子看護師長だ。「全身麻酔下の大きな手術ですので、私たちは常に患者さんの不安に寄り添うにしています」と、患者に最も近い立場できめ細かくサポートしている。
実際の手術は、愛知医科大学病院の主要な連携先の1つである名古屋セントラル病院の脳神経外科医長で、定位脳手術のベテランである竹林成典先生に指導的立場で参加してもらっている。 「当院からは私のほかに脳外科の若手医師も加わり、3名で手術を行います。術中の神経学的検査、副作用の確認などは斎木先生と田口先生にお願いしています。このように神経内科医と脳神経外科医が協力して手術を行います」と、名倉講師が充実した手術体制を紹介する。
手術に要する時間は概ね5〜6時間。小出看護師長らは、患者が病棟に戻る時間などを確認しながら、滞りなく入院生活が送れるように病棟環境を整えている。DBS患者のケアに主にかかわる病棟看護師は、パーキンソン担当として一定の勉強やトレーニングを終えた4名で、さらに育成中という。
DBS導入後は定期的に通院してもらうか、他の医療機関との連携でフォローし、動作チェック、調整、患者によっては機器の交換などを行う。パーキンソン病総合治療センターを開設して以降、2022年12月までのDBS導入件数は12件となっている。
「退院後、手先を使う職人として仕事に復帰した患者さん、大好きなゴルフを再開して楽しんでいる患者さんなど、DBSによって人生を取り戻す例はたくさんあります」と斎木教授が言うように、DBSは患者のQOL向上に大きく寄与している。
4. 多職種連携による経腸療法
薬剤師を中心に多職種が連携
1週間の体験入院を経て導入し外来でフォロー
経腸療法に中心的にかかわっているのは近藤あゆみ薬剤師だ。近藤薬剤師は神経内科病棟担当薬剤師でもあり、パーキンソン病患者に日常的に接している。
「経腸療法の導入に際しては、パーキンソン病総合治療センターの医師、神経内科の看護師、消化器内科医、製薬メーカーの担当者、薬剤師がしっかり協力しています。また、特殊な薬剤を使うため、薬局の協力が不可欠で、患者さんの利用しやすい薬局を見つけたり、患者さんが施設を利用している場合には、その施設に製薬メーカーの担当者から説明に行ってもらうなど、患者さんが安心して過ごせるよう工夫しています」と近藤薬剤師が言う。
経腸療法の導入を検討中の患者には、あらかじめ体験入院をしてもらう。胃ろうに代わって鼻から挿入したチューブから薬液を注入し、効果を体験してもらうのである。斎木教授は、「治療効果という意味ではDBSによく似ていますが、脳に電極を埋め込む必要がないため、患者さんの適用範囲は比較的広くなっています。ただし、胃ろうをつくることに抵抗感を示す患者さんも少なくないので、まずは装置の使い勝手や効果を体験していただくことにしています」と説明。介護者の役割についても看護師からよく説明し、そのうえで導入するかどうかを決めてもらっているという。
経腸療法導入に関するプロトコルは田口医師が作成し、医療連携マニュアルについては薬剤師と看護師が協力して作成するなど、システムを構築している。看護師同士の連携もその一環で、「導入後、チューブの閉塞などのトラブルや、そのほか患者さんに困りごとが生じた場合には、基本的に外来看護師が対応しますので、そこで適切に対応できるように病棟看護師が指導したり、体験入院時の患者さんの様子などを伝えたりしています」と小出看護師長が言う。
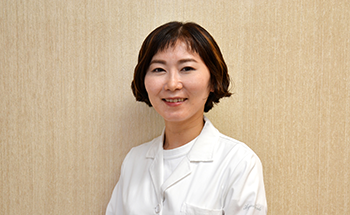
近藤あゆみ 神経内科病棟担当薬剤師
5. 調整のための入院
薬剤師、看護師、リハビリスタッフの目を活かし
薬剤の量や投与間隔、刺激の強さを適切に調整
検査入院や経腸療法体験入院のほかにも、すでにパーキンソン病と診断され、治療中の患者に、薬剤の調整や、DBSの刺激を調整する目的で入院してもらうこともある。こうした入院では、「薬剤師や看護師の目が非常に大事」と斎木教授は指摘する。パーキンソン病患者の薬物療法では薬の量や投与間隔が、DBSでは刺激の設定が病状によって違ううえ、病状に合わせて変化させていかねばならないからだ。
「患者さんを見ていて、薬が効き過ぎているのではないか、処方された薬をきちんと使用できていないのではないかと思われた場合は速やかに医師に伝え、対応を検討していただきます。また、薬の使い方を自分なりに工夫されている患者さんも少なくないので、そういう場合はどうすれば適正な使い方ができるかを患者さんと一緒に考えます」と近藤薬剤師が言う。
近藤薬剤師は、勤務時間の多くを神経内科病棟で過ごしている立場を活かし、患者と積極的にコミュニケーションを図りながら経時的な変化を観察している。そして、薬に関係のないことでも、気づいたことがあれば病棟看護師に伝え共有する。また、患者が主観的に語ることが正しいかどうかを知るために、リハビリスタッフと意見交換をすることもしばしばだという。
看護師の視点については小出看護師長が、「治療内容も日常生活援助の方法も個別性が非常に高いので、一人ひとりの思いに寄り添うことが本当に大事だと感じます。オン・オフの状態が薬や脳への刺激によってきちんとコントロールできているか、オフのときに私たち看護師がどのような援助をすべきかなども、患者さんそれぞれについて医師やリハビリスタッフに相談しながら、適切に行うことを心がけています」と話す。
斎木教授は病棟スタッフの対応能力を上げるため、こうした日頃の業務の中で指導するほか、パーキンソン病について基礎から学ぶハイブリット形式の勉強会を月に1回ペースで開催している。
6. リハビリテーション
病棟リハ室を活用して入院患者の評価と訓練
近隣病院の協力で入院リハビリも提供
検査目的であれ、治療中の調整目的であれ、入院患者にはできる限りリハビリテーションを提供する。パーキンソン病患者のリハビリに携わるスタッフは、理学療法士8名、作業療法士6名、言語聴覚士5名である。入院中のリハビリの目的は、患者の評価と訓練。これについては、リハビリテーション部の河尻博幸副技師長(理学療法士)が次のように紹介する。
「運動機能や高次脳機能、日常生活動作の機能などを評価し、評価結果を医師と共有して意見交換しながら、一人ひとりに合ったリハビリを提供していきます。その際には、患者さんの運動能力をできるだけ押し上げ、少しでも日常動作がしやすくなるよう配慮します」
斎木教授は、リハビリスタッフによって行われている簡易認知機能検査や自律神経機能の評価を重視していると言い、「認知機能を調べることは、患者さんの能力を知ることでもあり、パーキンソン病の病状そのものを知ることでもあります。また、自律神経失調の1つである起立性低血圧の有無や程度を調べることは、診断の参考にもなりますし、患者さんのQOLを維持するための指標にもなるので、とても重要なのです」と解説する。
また、「パーキンソン病や関連疾患の患者さんは運動量が低下しているため、発症時点で必ず運動能力が低下しています。ですので、リハビリによって運動能力、特に下肢筋力を向上させることが非常に大事です」と、パーキンソン病の診療におけるリハビリの重要性を強調する。
入院患者のリハビリは、病院3階にあるリハビリテーションセンター、リハビリテーション庭園などで行っており、神経内科の病棟内に設けた病棟リハビリテーション室も活用している。「病棟リハ室には、一般的なリハビリ機器のほかに、起立性低血圧を調べる起立台、各種評価のための道具なども完備しています。患者さんは入院中、病室と病棟リハ室を頻繁に行き来しながら、生活の中でリハビリを行うことができる環境です」と河尻副技師長。なお、この病棟リハ室は、2014年に竣工した新病院に設計段階から盛り込まれたものだ。
大学病院の特性から、リハビリ目的の長期入院を受け入れることは難しいが、集中してリハビリを行うことが望ましい患者には、同じ地域にあってリハビリに強いメイトウホスピタルの協力により入院リハビリを提供している。メイトウホスピタルは東海地方では珍しく、大きな動きで知られるLSVT®BIGに本格的に取り組んでいる。斎木教授がこの病院で週に1回診察していることもあり、連携はとてもスムーズだ。

河尻 博幸 リハビリテーション部 副技師長

リハビリテーションセンター

リハビリテーション庭園


神経内科病棟に設けられた「病棟リハビリテーション室」
7. 今後の課題・展望
人材育成、患者への啓発、広報活動などを充実
"パーキンソン病なら愛知医大"と言われる存在に
今後の抱負として田口医師は、デバイス治療に用いる各種機器の評価、扱い方について、学会などを通して積極的に発信していくことを挙げる。同じく名倉講師は、DBSのパーキンソン病以外の疾患、たとえばてんかん治療などに応用することを考えている。
斎木教授は「デバイス治療を核として、当院のパーキンソン病治療を盛り上げていくという私自身に課せられた使命をしっかりと果たしていきたい」としたうえで、「パーキンソン病の治療に一生懸命に取り組む人材を増やしていきたい。特に若い世代の医師や看護師、リハビリスタッフを育てていきたいと思っています」と語る。人材育成の一環としては、パーキンソン病療養指導士の資格取得を推奨。リハビリスタッフを中心にすでに複数が取得済みだ。
「私たちの目標を一言で言えば、"パーキンソン病なら愛知医大"と言われるくらいの存在になること」と斎木教授。そのためにも、診療の質をより高めながら、市民啓発や広報活動にも力を入れていく構えだ。手始めに、パーキンソン病総合治療センターのパンフレットを作成。院内の健康情報室「愛スマイル」と連携し、患者が情報や商品にアクセスしやすいシステムづくりも進めている。
2022年10月には、オンライン形式のDBS相談会もスタートさせた。パーキンソン患者とその家族を対象に、同センターの医師3名がDBSを紹介するもので、個別の質問にも答えるため参加者は1回6組に限定。DBSに興味を持ちながらも受診には至っていない患者に、早期の受診を促す狙いもある。
こうした多面的な取り組みを継続することで愛知医科大学病院パーキンソン病総合治療センターの存在を知ってもらい、患者がより早く、より良い医療にアクセスできるようになることを目指している。

パーキンソン病総合治療センターでともに仕事をする皆さん。右から3番めが小出愛子看護師長
KKC-2023-00010-3
パーキンソン病 med.front
-
2024年2月9日公開/2024年2月作成
-
2023年11月6日公開/2023年11月作成
-
2023年10月6日公開/2023年10月作成
-
2023年7月14日公開/2023年7月作成
-
2023年2月22日公開/2023年2月作成
-
2023年2月21日公開/2023年2月作成
おすすめ情報
-
おすすめ情報は、協和キリンのウェブサイトにおける個人情報の取扱い方針に基づき、お客様が閲覧したページのアクセス情報を取得し、一定の条件に基づき自動的に表示しています。
そのため、現在ご覧いただいているページの情報との関連性を示唆するものではございません。












 ®の有効性・安全性~アデノシンA2A受容体を介した作用機序~」公開 のサムネイル画像">
®の有効性・安全性~アデノシンA2A受容体を介した作用機序~」公開 のサムネイル画像">