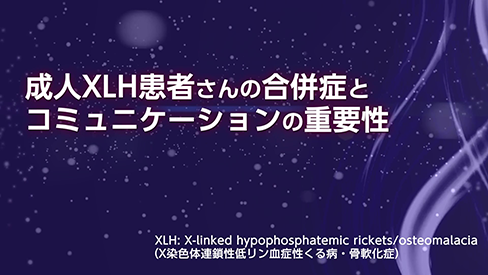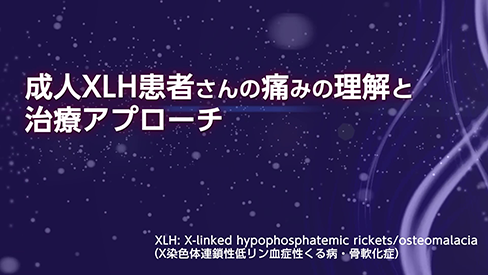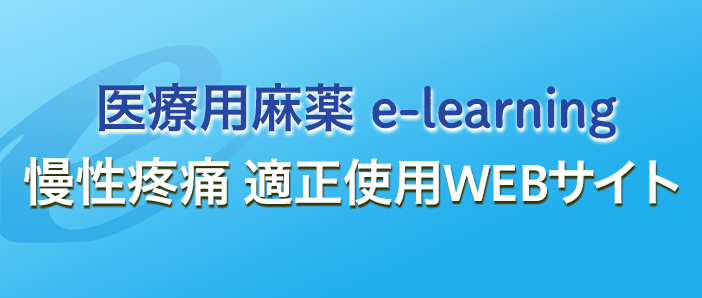帝京大学ちば総合医療センター
[希少疾病診療~未来への扉~]
2025年4月1日公開/2025年4月作成

- ●病院長:井上 大輔 先生
- ●開設:1986年
- ●所在地:千葉県市原市姉崎3426-3
成人と小児の専門医が揃った強みを生かし、
骨系統分野の希少疾患の診療に取り組む
1986年に開院した帝京大学ちば総合医療センターは、地域の中核病院としての役割を果たしてきた。大学病院の分院として希少疾患にも対応しており、骨系統疾患の成人では内分泌代謝内科が、小児では小児科が診療にあたっている。成人では整形外科や歯科からの紹介のほか、小児期に見逃がされていた軽症患者の拾い上げにも積極的に取り組んでおり、小児では、一般小児科医や健診で拾い上げられた紹介患者を中心に診療を行っている。同センターは成人と小児の骨系統疾患の専門医が在籍する、国内でも稀有な施設の一つで、小児から成人の移行期における連携も始まっている。
1. 内分泌代謝内科の特徴
骨・カルシウム代謝の専門医を中心に
軽症の潜在患者を拾い上げる

井上大輔 帝京大学ちば総合医療センター病院長/第三内科学講座 主任教授
帝京大学ちば総合医療センターは、市原市の誘致により1986年に開院した。現在は475床を有し、地域救命救急医療センター、地域支援病院など、さまざまな機能を担い、地域の中核病院としての役割を果たしている。大学病院の分院として希少疾患にも対応しており、骨系統疾患については、成人では内分泌代謝内科が、小児では小児科が診療にあたる。
内分泌代謝内科を率いる井上大輔教授(病院長兼務)は、同科の特徴について次のように説明する。「当科では代謝性疾患を主に扱い、その中でも最も多いのは糖尿病で、診療全体の6割を占めます。外来患者数は年間1万人以上、入院患者数は年間300人程度です。これらの診療を私のほか、講師クラスの医師が2名、後期研修医2名の計5名で行っています」。
井上教授自身は骨・カルシウム代謝の専門家で、日常的に骨粗しょう症の診療にも従事するが、専門外来は設置していない。「この病気の特徴として、ある一定の年齢以上になると、どの人もリスクが高まってきます。そのため、糖尿病などで通院している患者さんの中からハイリスク者を拾い出し、骨粗しょう症の治療を行っています。その中から希少疾患などが発見されることもあります」と井上教授は説明する。
また、本来は小児期に骨系統疾患を発症していたけれど、軽症のために発見されず、成人になってから骨粗しょう症を疑われて同科に紹介されるというパターンもある。「紹介患者が骨折していて骨量も低いということになれば、骨粗しょう症であるとすんなり診断することがほとんどだと思いますが、診断時において注意しなければならないのは骨系統疾患との鑑別です。当科では骨粗しょう症で紹介されてきても血液検査を実施し、血液中のリンやアルカリフォスファターゼ、必要に応じてFGF23なども測定しています」と井上教授は診断のポイントを示す。そして、骨粗しょう症と診断しても、その治療に効果がないときは骨系統希少疾患を疑ってみることが必要とも言う。「こうしたケースはごく稀だと思いますが、ないわけではありません」(井上教授)。
整形外科、歯科など他科からの紹介患者を含め、現在、内分泌代謝内科が継続診療している希少疾患患者は20~30人程度だ。その大半は、比較的軽症で生命予後もよい。ただし、痛みを伴うことが多く、QOLが低下しているため、治療においては痛みの改善に努めている。また、小児期に起こった骨変形を放置したことによる影響や、骨粗しょう症とは異なる骨折を繰り返す患者もいて、整形外科との連携が欠かせない場合もある。「高齢期になると要介護の原因にもなってきますので、こういったことも視野に入れながら骨系統疾患による症状を悪化させないことを目標に治療しています」(井上教授)。
2. 小児科の特徴
日常の血液検査を
骨系統疾患の拾い上げに活用する

南谷幹史 帝京大学ちば総合医療センター小児科病院教授
小児科は、地域の小児医療の中核施設として救急医療と入院医療を担っている。「市原市の人口減に伴って出生数も減少しており、外来・入院ともに患者数が減っています。外来患者数は年間6,000~7,000人、入院患者数は350~400人です。夜間の救急外来を千葉ろうさい病院、千葉県こども病院、千葉市立海浜病院と輪番制で行っており、1カ月の日数にすると約12日(4割弱)前後担当しています。そのため、外来患者数の中には夜間救急外来で受診した子どもたちも多いです。入院患者は呼吸器症状や消化器症状を伴う感染症が多く、喘息、熱性けいれん、川崎病なども目立ちます。また、産婦人科では異常分娩を積極的に受け入れていることもあり、新生児の入院が多いのも一つの特徴です」と南谷幹史小児科教授は説明する。
小児科のスタッフは、南谷教授を含め総勢5名で、准教授クラスの医師が1名、助手クラスの医師が3名在籍する。このうち、内分泌疾患の専門医が2名、感染症の専門医が2名、そして児童精神科の専門医が1名いる。「内分泌疾患や児童精神科の領域については紹介患者さんも多いです」(南谷教授)。
南谷教授の専門である内分泌領域における希少疾患のうち、紹介患者は骨系統疾患や甲状腺関連疾患が多い。また、骨形成不全症に関しては30年にわたって診療してきたこともあり、南谷教授のもとに県内から患者が集まってきている状況である。現在、継続的に診療している希少疾患をもつ子どもたちは20名程度だ。
「副腎関連疾患など新生児スクリーニング検査で見つかりやすくなっている疾患がある一方で、血液検査をしていても見逃がされる希少疾患も少なくないのです」と南谷教授は指摘する。その原因は複数あり、一つは小児科医の知識や関心がうすい場合だ。てんかんでフォローされている子どもの血液検査データでカルシウムの数値が低くても、そのことに小児科医が気づけなければ希少疾患を見逃がすことがある。また、成長発達の過程にある小児の場合、小児科専門医であったとしても検査データを正しく判断するのはとても難しい。
骨形成不全症は、胎児期あるいは新生児期など早期から多発性骨折が起こっていれば診断がつきやすい。それでも虐待による骨折との鑑別が必要だと南谷教授は診断のポイントを挙げる。「軽症の場合は見逃されていることも多く、井上教授からの説明があったように、ある程度、成長してから若年性の骨粗しょう症を疑われて内科で見つかるケースも少なくないのです」(南谷教授)。
このような診断の現状がある中、小児科では日常診療のルーチン業務を骨系統疾患の拾い上げに役立てている。「当科では患者の採血をする場合、リン、アルカリフォスファターゼ、血液ガス分析を必ず調べるようにしています。この目的は、子どもたちの栄養状態を確認したいからですが、血液検査でこれらの数値に異常が検出されたときは内分泌専門医に必ず相談してもらうシステムにしています」と南谷教授は説明する。
3. 移行期の連携
連携体制を整えることで
治療中断や病識向上の効果も期待
小児科では、骨系統疾患を治療するにあたり、できるだけ身体的障がいを来たさないことを目標に取り組んできた。一方で、治療薬による合併症を引き起こすこともあり、そのバランスを保つことに苦慮してきた歴史があるという。
「ある疾患は治療法が確立されていたものの、治療薬の過剰投与になりがちで、成人したころにはかなりの確率で合併症をきたしていました。それだけに新薬の登場が待ち遠しいものがありました」と南谷教授は振り返る。
新薬による治療によって合併症の不安はなくなったものの、男女で治療効果に違いがみられることもわかってきたので、今後は性別によって薬の量を変えるなどの使い方を見直していく必要があると南谷教授は感じている。
成人後の治療移行も重要な課題として残されている。「それぞれの医療機関によって状況は異なりますが、小児科が生涯にわたってフォローしているのが現状です。しかし、成人期は小児期とは異なる合併症が起こってきます。また、筋力低下のように小児期では問題にならなかったことが、成人期では大きな問題になるようです」と南谷教授は指摘する。
同センターの場合は、内分泌代謝内科に骨・カルシウム代謝の専門家である井上教授がいるため、小児科と内分泌代謝内科で移行期の連携が始まっている。だが、このような医療機関は稀有な存在だ。南谷教授は移行期の連携体制を整えることで治療のドロップアウトを防いだり患者の病識を高めていく効果にも期待する。「身長の伸びが止まると治療のステージが変わるため、その頃にドロップアウトしてしまう子どもたちが少なくありません。先日もドロップアウトした骨系統疾患に罹患している患者さんが母親になり、生まれた子どもに遺伝していないかどうかを診療してほしいと10年ぶりに受診してきました。子どもは問題なかったのですが、治療を中断した母親の骨量を調べてみるとかなり低い。治療を再開するようにすすめたのですが、また「私はいいです」と言ってドロップアウトしてしまいました。本人の病識を高めることの重要性を再認識しているところです」(南谷教授)。
4. 展望と課題
希少疾患の拾い上げに
情報提供を中心とした啓発活動が必須
成人も小児も骨系統の希少疾患をいかに拾い上げて専門医療機関につなげるのか、特に軽症についての対策が共通の課題だ。この一つの解決策として、井上教授も南谷教授も情報提供を中心とした啓発活動が欠かせないと口を揃える。「かつて骨粗しょう症は整形外科の病気という認識が強かったですが、さまざまな啓発活動の結果、内科医が代謝性疾患であることを意識するようになり、近年は内科医からの紹介も増えています。同様に他の骨系統疾患も啓発活動で内科医の認識を変え、疑わしい人には血液検査を実施するといった状況になることを望みます」と井上教授は語る。
一方、南谷教授はプライマリケア医のさらなる紹介に期待したいと言う。「親は子どものO脚を不安に思っていて、かかりつけの小児科医や近所の整形外科医に相談します。しかし、それを問題ないと判断して専門医に紹介しないケースが一定数あるのです。乳幼児健診においても同様の傾向がみられます」。この対策として、専門医に積極的に紹介してほしいと訴える。「低身長を疑う場合はすぐに紹介してくれますが、その9割は病気ではありません。でも、それでよいのです。2歳を過ぎてO脚があれば専門医に紹介してほしいと思います」(南谷教授)。
また、井上教授は拾い上げた患者をしっかり治療していくためには専門家の育成や多職種・多科連携体制を整えることも必要だと指摘する。成人の場合は、内分泌代謝内科を中心に整形外科、歯科、耳鼻咽喉科、栄養科、リハビリテーション科が連携して治療にあたる診療体制が理想的だという。さらに井上教授は「世界中の研究者たちが希少疾患に関心を持つようになり、かつ我が国では少子高齢化が進展しています。希少疾患対策は行政レベルも含め取り組まなければならない分野です。当センターにおいても自分たちの強みを生かしながら、この分野においても大学病院としての責務を果たしていきたいと考えています」と締め括った。

井上教授と南谷教授は、成人と小児の専門医が揃う強みを生かし、移行期の診療体制のモデルづくり にも取り組みたいと考えている
KKC-2025-00100-1
希少疾病診療~未来への扉~
-
2025年4月1日公開/2025年4月作成
-
2024年12月16日公開/2024年12月作成
-
2024年10月28日公開/2024年10月作成
-
2024年9月11日公開/2024年9月作成
-
2024年9月9日公開/2024年9月作成
-
2024年9月6日公開/2024年9月作成
-
2024年9月3日公開/2024年9月作成
-
2024年8月21日公開/2024年8月作成
おすすめ情報
-
おすすめ情報は、協和キリンのウェブサイトにおける個人情報の取扱い方針に基づき、お客様が閲覧したページのアクセス情報を取得し、一定の条件に基づき自動的に表示しています。
そのため、現在ご覧いただいているページの情報との関連性を示唆するものではございません。