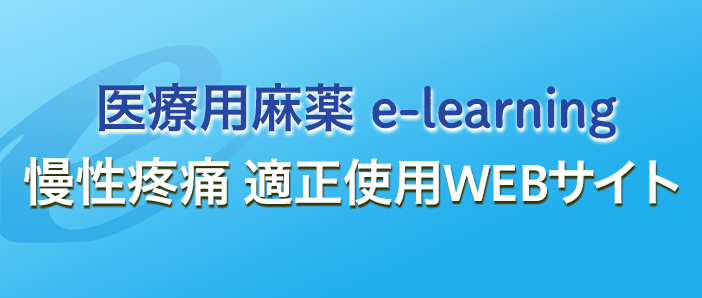順天堂大学医学部附属練馬病院
[パーキンソン病 med.front]
2022年11月29日公開/2022年11月作成

- ●院長:児島邦明先生
- ●開設:2005年
- ●所在地:東京都練馬区高野台3-1-10
治療の選択肢が多いことを強みに
個別性の高い専門診療を実践
順天堂大学医学部附属練馬病院脳神経内科は近年、パーキンソン病をはじめとする変性疾患の診療に重点を置き、脳深部刺激療法(DBS)やレボドパ・カルビドパ持続経腸療法(LCIG)など新領域の治療にも積極的に取り組んでいる。また、治療の選択肢が多く、かつ同一施設ですべての治療を完結できることも大きな特徴である。
1. 地域における役割
病床不足地域の基幹病院として
救急医療から高度医療まで提供
順天堂大学医学部附属練馬病院は、2005年に順天堂大学医学部に附属する6番目の病院として開院した。東京都内において練馬区は人口約74万人を有する大きな行政区だが、他区に比べて病院数および一般病床数が著しく不足していた。この積年の課題を解消するために、練馬区では新病院の誘致計画を進め、2001年に応募医療機関の中から学校法人順天堂を新病院の運営主体に選定した。
開設当時、院長として新病院を率いた宮野武名誉院長が同病院を「西のイージス艦」に例えたように、同病院では練馬区のみならず都区西部地域、多摩地域、関越道地域の基幹病院になるべく、開院以来、診療体制の充実に注力してきた。現在では、救急医療、小児医療、災害医療といった住民の安心と健康を守る基盤となる医療の提供に加え、がんの診断・治療を中心に最新の高度専門医療の提供にも積極的に取り組んでいる。また、順天堂大学大学院医学研究科が感染制御において文部科学省「21世紀COEプログラム」に選定されていることもあり、院内感染対策に重点を置いていることも大きな特徴の一つだ。
同時に地域医療支援病院として診療所や中小病院、保険薬局、介護施設、地域包括支援センターなどとの相互連携を強化。「ヒューマンブリッジ」と呼ばれる地域ネットワークシステムを通して、限られた医療・福祉資源の中、それぞれの役割を明確にし機能分担することで、効率的かつ効果的な医療の提供を行っている。
2. 診療科の特徴
変性疾患と脳卒中を二本柱に
脳神経疾患を幅広く診療

下 泰司 脳神経内科診療科長/順天堂大学大学院医学研究科 神経学教授/副院長
下 泰司脳神経内科診療科長(順天堂大学大学院医学研究科神経学教授/副院長)が率いる脳神経内科は、パーキンソン病、認知症を含めた変性疾患と脳卒中を二本柱に脳神経疾患を幅広く診療している。6人の脳神経内科専門医が中心となり、月に約1,300人程度の外来診療と入院および救急診療にあたっている。「高齢者が対象となる疾患が多いため、治療後の介護も踏まえたうえで総合的に対応していることが当科の特色の一つです」と下診療科長は説明する。
脳卒中は、脳神経外科、救急・集中治療科とともに当直に従事し、血栓溶解療法などの緊急治療を行う体制を構築している。また、治療後は地域のリハビリテーション病院に早い段階で紹介し、廃用性症候群を防ぎ、早期回復をサポートする。
順天堂大学医学部附属順天堂医院の脳神経内科はパーキンソン病の研究で世界的に評価されているが、同科も本院同様にパーキンソン病を得意とし、下診療科長をはじめ、パーキンソン病を専門とする医師が多いのが特徴だ。そのため、もともとパーキンソン病で受診する患者は多かったが、2019年に下診療科長が本院から着任した後はさらに倍増し、2022年現在では300~400人の患者が通院する。その患者数は区内の医療機関ではトップクラスだ。
また、パーキンソン病・不随意運動専門外来以外にも、ボツリヌス専門外来、DBS専門外来、もの忘れ専門外来といった専門外来を設置し、専門性の高い最先端の診療に取り組んでいる。「新たにてんかんの専門医が赴任してきたので、てんかん外来の開設も計画中です。今後もさまざまな機会を捉え、専門外来を増やしていくつもりです」と下診療科長は意向を語る。
3. パーキンソン病診療の特徴1
進行期のパーキンソン病に
最先端のDBS治療を実施
「パーキンソン病に関しては豊富な診療経験を有する医師が適切な治療法を選択し、最先端の治療を行えるという自負があります」と下診療科長は力強く言う。
同科では薬物治療だけでなく、脳深部刺激療法(DBS)、レボドパ・カルビドパ持続経腸療法(LCIG)など他施設ではそれほど導入されていない新領域の治療にも積極的に取り組み、パーキンソン病の治療に対する選択肢が多く、かつ同一施設ですべての治療を完結できることが大きな特徴となっている。
■脳深部刺激療法(DBS)
脳内に留置した電極と胸部の皮下に埋設した刺激発生装置を結線し、
電極を通じて脳内に電流を流して刺激を与え、症状を改善することを目的としている。
■レボドパ・カルビドパ持続経腸療法(LCIG)
胃ろうを造設して空腸までチューブを挿入し、そのチューブに体外式のポンプをつなぎ、
レボドパ・カルビドパ製剤を持続的に投与することにより症状の改善を図る。
なかでもDBSは、この治療のスペシャリストとして全国的に知られる下診療科長が着任したことにより近年、特に注力している分野だ。2020年10月には脳神経外科と連携し、世界に先駆けて開発された新タイプの刺激発生装置の導入に成功している。
進行期のパーキンソン病では、薬効の持続時間が徐々に短くなり、ウェアリングオフなどの症状を起こすため、服薬回数や投薬量を増やすことが必要になってくる。これらの処置によって生活の質が低下することも少なくなく、こうした患者を対象にDBSの導入が検討されるのだが、従来の刺激発生装置では脳内に電流を持続的に流す方法が行われてきた。
一方、これまでの研究から薬効が消失してパーキンソン病の症状が出現すると脳内の神経細胞の活動に異常が生じることがわかってきた。そこで、開発されたのが新タイプの刺激発生装置で、脳内のバイオマーカーを指標として神経細胞の活動が異常になったときのみ電流を流すことができるようになる可能性がある。
「この装置が登場したことで、常に電流を流すことによって生じていた副作用(不随意運動の発現やしびれ等)を軽減できるようになりました。また、脳内の神経細胞活動というバイオマーカーを記録することによって症状の変動を客観的に評価することも可能になりました」と下診療科長はメリットを説明する。
半面、新タイプの刺激発生装置は電池の充電ができず、4~5年で電池交換が必要になる。そのため、60代後半の患者が適応となり、それより若い患者には10~20年と電池交換年数の長い充電式の従来型のほうが望ましいという。「複数の選択肢があることが当科の最大の強みです。DBSにおいても患者さんの年齢、症状、生活状況、既往症などを勘案しながらカンファレンスの場で検討し、その人に最適な刺激発生装置を選択したうえで、最終的には患者さんに選んでもらいます」(下診療科長)
2020年にDBSを開始して以来、同科では20人程度に実施してきたが、このうち新タイプの刺激発生装置を導入したのは10人前後だという。「バイオマーカーを活用することで、より個別性の高い治療が可能になりましたが、どのような状態や状況の患者さんに有効性が高いのか、あるいは難治性のパーキンソン病にも効果があるのかといったことは、これからデータを蓄積し、検証していく必要があります」と下診療科長は新治療におけるエビデンスの創出にも意欲的だ。
4. パーキンソン病診療の特徴2
地域から難治性患者を受け入れ
紹介元の医療機関と連携して診療
一方、同科ではLCIGにも取り組んでおり、これまでに4人の患者に実施している。「本院では60人程度の実施例がありますが、どの進行例にも適応できるものではなく、この治療を行うには消化器外科との連携を含め、医師の経験値も必要です」と下診療科長は指摘する。
LCIGの目的もDBSと同じで、進行期のパーキンソン病のウェアリングオフ症状を改善し、随意運動を起こさないようにすることだ。この治療は、体内に電極や刺激発生装を埋め込むDBSより侵襲性や負担は低いものの、体外式ポンプに液体状の薬剤をセットし、自分自身または介護者がスタートボタンを押すなどの自己管理が必要になるため、治療の適応となる患者は限られるという。「適応者が少なくても、患者さんにとって選択肢が一つでも多い治療環境を整備することは高度専門医療を提供する大学病院の使命であると考えます」(下診療科長)
DBSやLCIGに対する一定のニーズはあるため、同科で取り組んでいることが広く認知されることにより、パーキンソン病を専門とする脳神経内科の診療所のほか総合病院などからも難治性の患者が紹介されてくることが増えてきた。DBSの場合は、電極や刺激発生装置などを埋め込む手術の後、電流や薬剤の細かい調整をしながら症状が落ち着くのに約半年から1年かかる。症状が安定したら紹介元の医療機関に普段のアフターフォローを依頼し、同科は半年に1回程度の頻度で電流や薬剤の再調整を行うようにしているが、アフターフォローに対応できない医療機関も少なくなく、この指導も一つの課題になってきているという。
「2006年に順天堂医院でDBSを開始した頃は、術後に管理をするのは執刀した脳神経外科医の役割といった風潮が強かったのですが、薬剤の服薬回数や投与量を調整するのは脳神経内科医が得意とするところです。そのため、近年は脳神経内科医でアフターフォローしようという動きが出てきて、特に若手医師の関心が高くなっています。DBSはどこの施設でも対応できる治療法ではないものの、脳神経内科医として電流の調整を含め、一通りの知識は持っておいてほしいと思います」と下診療科長は話す。
5. 展望と課題
パーキンソン病に熟知したスタッフを
育成し、チーム医療の強化を目指す
「当科は順天堂の6つの附属病院の脳神経内科の中でパーキンソン病をはじめとする変性疾患の重点医療機関として位置づけられています。そのため、この分野に関してはリハビリテーションを含め、総合的かつ包括的に診療できる体制をさらに強化していきたいと考えています」と下診療科長は展望を語る。
その強化策の一つとして、本院のようにパーキンソン病に熟知したチームを編成することを目指しており、看護師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士など医療スタッフの育成が目下の課題だ。
また、DBSやLCIGなどを受けた患者を地域でサポートできるよう在宅医との連携にも注力していくため、「区医師会の在宅医療に関する勉強会などを通して積極的に情報発信しています」と下診療科長は言う。
超高齢社会の到来とともに、80代でパーキンソン病を発症する高齢者も増えており、これからパーキンソン病を得意とする脳神経内科へのニーズはますます高まってくることだろう。順天堂大学医学部附属練馬病院には、この分野においても「西のイージス艦」として役割が大いに期待されている。
KKC-2022-01066-1
パーキンソン病 med.front
-
2024年2月9日公開/2024年2月作成
-
2023年11月6日公開/2023年11月作成
-
2023年10月6日公開/2023年10月作成
-
2023年7月14日公開/2023年7月作成
-
2023年2月22日公開/2023年2月作成
-
2023年2月21日公開/2023年2月作成
-
2022年11月29日公開/2022年11月作成
-
2022年11月15日公開/2022年11月作成













 ®テープの薬物動態と臨床成績」公開 のサムネイル画像">
®テープの薬物動態と臨床成績」公開 のサムネイル画像"> ®テープの役割 ―患者ごとにあわせた至適用量調整のポイント―」公開 のサムネイル画像">
®テープの役割 ―患者ごとにあわせた至適用量調整のポイント―」公開 のサムネイル画像">