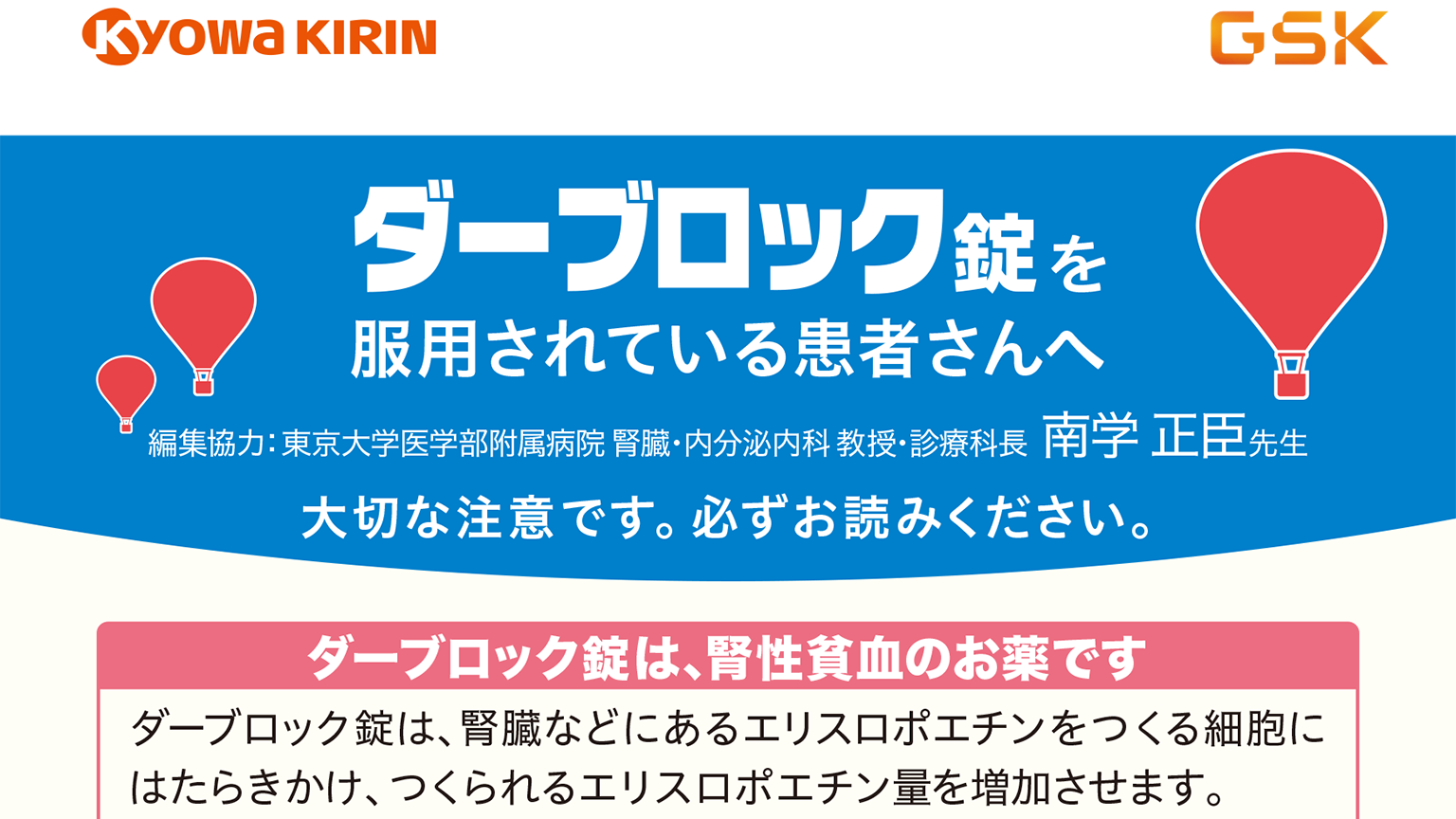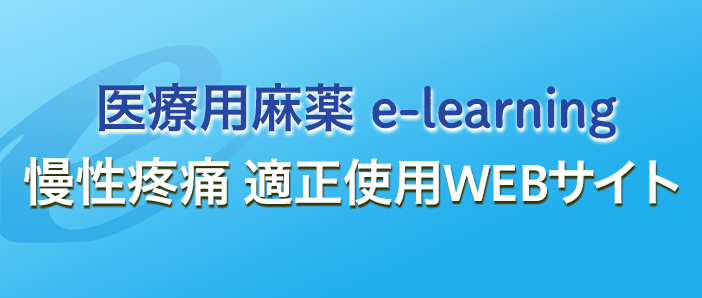社会医療法人創和会 しげい腎クリニック早島
[透析施設最前線]
2025年11月4日公開/2025年11月作成

- ●院長:松原 龍也 先生
- ●開設:2024年
- ●所在地:岡山県都窪郡早島町前潟277
チームで「攻めの透析」を展開し、
いきいきとした透析ライフを支える
透析医療の黎明期ともいえる1968年11月に岡山県初となる試験的透析を開始。以来、岡山県倉敷市を中心に透析医療・腎医療の発展に貢献してきた社会医療法人創和会。2024年10月に同法人初となる透析専門のクリニック『しげい腎クリニック早島』を開設。「エンジョイ 透析ライフ」のスローガンのもと、透析になっても患者がいきいきと暮らせるように「攻めの透析」を展開し、チーム医療で透析患者を支えている。
1. クリニックの概要と特徴
法人初となる透析専門クリニックを開院
最新かつ最良の施設を目指す

松原 龍也 院長
しげい腎クリニック早島は、2024年10月、社会医療法人創和会(岡山県倉敷市)で初となる透析専門のクリニックとして開設された。同法人は1968年から透析医療に積極的に取り組んでおり、法人が運営するしげい病院、重井医学研究所附属病院、幸町記念病院の3病院は現在、岡山県下で同時透析数の1位から3位を占めている。一方で、3病院は外来透析患者を受け入れる収容能力が限界を迎えつつあり、近年、新たに透析専門のサテライトクリニックを建設する必要に迫られていた。同時に、透析患者の状態に応じた適切な医療を提供するために、比較的元気で自分で通院できる患者はクリニックで対応し、入院が必要な患者は病院で手厚いケアと治療を行う診療体制を、法人全体で構築することも大きな目的の一つだった。
「クリニック建設にあたっては、それぞれの病院に通院していた患者さんが通いやすいように、中間地点となる早島町を選定しました。バイパスが近く、岡山と倉敷を結ぶ幹線道路が新しく造られる計画もあり、交通の便がよいことが決め手になりました」と松原龍也院長は説明する。
常勤スタッフは、医師1名、看護師4名、臨床工学技士5名、事務職2名で、いずれも10年以上のキャリアを持ち、病院勤務の経験がある。「最新かつ最良の透析クリニックを作りたいという目標があったので、法人内の各施設からチャレンジ精神にあふれる意欲的なスタッフを抜擢し、ここに集めました」と話すのは田中昭彦統括マネジャーだ。重井医学研究所附属病院で臨床工学技士長として現場を率いた後、事務部門に異動し、新クリニックのプロジェクトが決定した当初から土地の選定、地域の医療状況の調査、建物の設計、クリニックのコンセプトづくりなどに一貫して関わってきた。
こうして数年の準備期間を経て、オープンしたクリニックの1階に位置する透析室のベッド数は30床。患者が快適に過ごせる環境を重視し、室内はウッド調の建具や床材で統一、落ち着いた空間を演出している。また、患者のプライバシーにも配慮し、個々の透析スペースは半個室タイプにしているが、スタッフが患者の様子を観察できるようにベッド間の仕切りはすりガラスになっている。透析ベッドは、フランスベッド社製のリクライニング機能を備えたタイプを採用。体を起こしたときにベッドの背もたれが体を包み込むような感じになるので、楽な姿勢を取れることが大きな特徴である。 「透析中に本を読んだり、タブレット端末で動画を視聴したり、パソコンで仕事をしたりするなど、患者さんが普段過ごしているような時間を持てるように透析ベッドにはこだわりました」と透析室の環境整備を中心的に行ってきた看護師の松田佳子マネジャーは説明する。
透析の質にもこだわり、グループ病院と同じ血液透析装置を配備するほか、医療材料も同じものを使用する。田中統括マネジャーとともに透析機械室の設計や機器の選定に携わった臨床工学技士の武智和希副主任によると、機械室も最新の設備を導入しているという。 「機械室内に粉末透析液の粉塵が飛散し、機械のファンなどに付着して不具合を起こすという報告を踏まえ、その対策として換気扇のダクトを機械類の直近に設置して粉塵の飛散を最小限に抑えたり、溶解装置の周りをカーテンで囲い、粉塵の付着を防いだりする工夫も行っています」(武智副主任)。

田中昭彦 統括マネジャー/臨床工学技士

松田 佳子 マネジャー/看護師

武智 和希 副主任/臨床工学技士

患者のプライバシーに配慮した半個室タイプの透析室。隣との仕切りはすりガラスを採用し、リクライニング機能を備えた透析ベッドで快適性も追求


透析機械室。粉末透析液の粉塵飛散対策として換気扇ダクトを機械類の直近に設置し、粉塵が付着しないように溶解装置の周りをカーテンで囲うことができる(右写真)


当クリニックはSDGsに積極的に取り組んでおり、敷地内緑化を推進している(左写真)。また、持続的な電力供給を目指し、屋上には太陽光パネルが設置され12月の稼働に向けて準備中(右写真)

透析液の排液を透析用水の加温に利用するヒートポンプを導入し、消費電力節減対策にも取り組んでいる
2. 早朝透析
患者の「エンジョイ 透析ライフ」を支え、
栄養状態改善の可能性に期待
比較的元気で自立している患者が中心の同クリニックは、十分な栄養、至適透析そしてcarpe diem(今を生きる)を3本柱に健康寿命の延伸をメインテーマとして診療にあたっている。同クリニックの特徴と魅力を簡潔かつ印象的に伝えるため、スローガンが考案された。それが古代ローマの詩人、ホラティウスの詩にあるcarpe diem(今を生きる)を同クリニック用に意訳した「エンジョイ透析ライフ」である。このスローガンに込められた思いを松原院長は次のように語る。
「透析医療のめざましい進歩とともに透析導入後も何十年と長生きする時代になりました。だからこそ、患者さんには透析になっても生きがいを持って自分の人生を楽しんでほしいのです。そして、私たちはそのエンジョイライフを支えられる透析クリニックでありたいと考えました」。
このスローガンを実践するために、開院当初から午前7時半に透析をスタートする「早朝透析」に積極的に取り組んでいる。「昼前には透析が終了するため、患者さんは午後から自分の好きなことができて1日の時間を有効に使えます」と松原院長は患者にもたらす早朝透析のメリットを話す。さらに体調を維持するうえでもよい効果がある。それは昼食がしっかり食べられることだ。一般的な透析のスケジュールは昼食の時間帯にかかるため、透析日は昼食を抜いてしまう患者が少なくない。このような生活を週3日続けていると、高齢者の場合は特に栄養状態がだんだん悪くなっていくという。
こうした課題を踏まえ、松田マネジャーと武智副主任は栄養面における早朝透析の効果を検討するために開院時から患者の栄養状態のデータ(血液検査)を定期的に取ってきた。すると、開院から半年しか経っていないにも関わらず、栄養状態が改善している患者が増えていた。「早朝透析の効果に加え、日頃から院長が患者さんに『しっかり食べてください』と指導していることも大きいです」と松田マネジャーは話す。この食事指導の方針について、松原院長は「高齢者の場合は、栄養が足りないと低栄養になり、フレイルやサルコペニア、認知症などを引き起こすおそれがあり、予後にも影響します。健康寿命の延伸からいってもしっかり食べてもらうことが大事なのです。それで数値が上がってくるリンなどに対しては薬剤でコントロールする"攻めの透析"を診療の基本としています」と説明する。
ただ現状は、早朝透析のある同クリニックを選択する患者がそれほど多くないため、そのメリットを実感してもらうために『オープンクリニック』にも積極的に取り組んでいる。「長年、グループ病院で透析を受けてきて慣れ親しんだスタッフや環境を変えるのは簡単なことではありません。そのため早朝の交通量の少なさを含め、早朝透析のプロセスを実際に体験してもらうことが重要だと思っています」と武智副主任は指摘する。グループ病院と連携し、患者が希望する日にいつでも早朝透析の"お試し"を受け入れる。「当クリニックは透析室への入室を15分間隔で刻み、最大でも3枠しか設定していないため、待ち時間がまったくありません。透析予定時間にスムーズに開始できる点も患者さんには大きなメリットといえます」(武智副主任)。

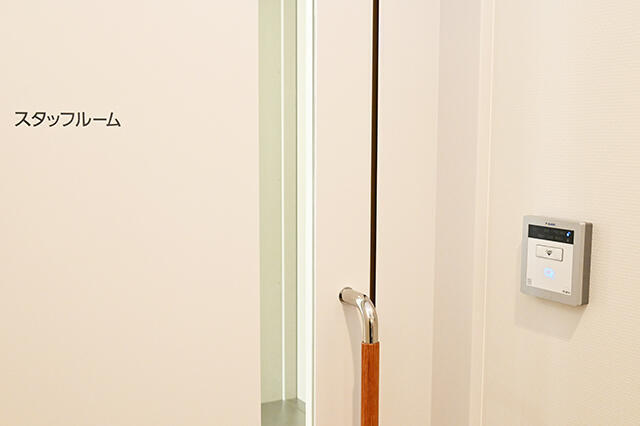
セキュリティ対策万全で快適な空間が広がるスタッフルーム。「エンジョイ 透析ライフ」を支えるためにスタッフにも働きやすい環境を提供することも大切にしている
3. 院内連携・地域連携
クリニックの強みを生かした院内連携を展開
課題解決にはグループ病院を活用
2025年5月現在、同クリニックがサポートする血液透析患者は40名弱で、早島町を中心に隣接する倉敷市、岡山市から通院する人も少なくない。平均年齢は70歳を超え、80代の患者が主流だ。こうした背景の中、透析室では医師・看護師・臨床工学技士が緊密に連携して患者を支えている。「スタッフ全員が揃う機会は限られており、定期的なカンファレンスを開催しにくい半面、透析管理中にスタッフが自然に集まって気になる患者さんについて話し合う場面は日頃からよくみられます」と松田マネジャーは話す。そして、その場で出てきた意見をもとに対応法を決め、スピーディーに実行に移せる行動力もあるという。
「透析条件を決める際も、臨床工学技士が分析した血液検査のデータを看護師が収集してきた患者情報とすり合わせたうえで、両者で最適解を出し、医師にフィードバックしています。スタッフ間の情報交換が早くフットワークがいいので、一人ひとりに丁寧に接することができるため、病院で働いていた頃に比べると患者さんにより近い位置でサポートできていることを感じます」と武智副主任も手応えを語る。
一方で、クリニックでは患者に常時関わる職種が限られてしまうことが課題だが、そこはグループ病院があるメリットを活かしている。「薬剤師、管理栄養士、リハビリ職がいないため、必要に応じて法人内の施設から派遣してもらっています。なかでも低栄養を防ぐために管理栄養士や言語聴覚士にサポートを依頼することが多いです。クリニックだからできないではなく、病院と同レベルの治療の質とサービスを提供したいのです」と松田マネジャー。
さらに、自分たちで行える工夫として地域の医療施設との連携に目を向ける。例えば、保険薬局と協働し、ポリファーマシー対策に取り組みたい意向もその一つ。「合併症の発症をきっかけに体力が低下することが多く予後にも悪影響を及ぼすため、できるだけ早期に合併症を発見することに力を入れています。この場合、当クリニックの診療機能では対応しきれないため、地域の医療機関との連携を基本にしています」と松原院長は説明する。定期検査に加え、循環器疾患を特に重視し、合併症の早期発見・早期治療に対応してくれる医療機関との連携強化に取り組んでいる。
看護師を中心にフットケアにも注力しており、院内にはフットケア専用室が設けられている。クリニックの設計に関わったベテラン看護師2名が長年の経験からフットケア専用室の必要性を進言し、実現したという。「今のところ透析患者さんが比較的元気なので足の状態はよく、ベッドサイドで足の状態を確認し必要なケアを指導することが中心ですが、糖尿病を併存している患者さんも多く、将来的にはフットケア専用室を活用する機会が増えると見込んでいます」と松田マネジャーは説明する。

透析室に隣接して設けられたフットケア専用室。機械室同様、ここにも換気扇ダクトが設置されている
4. 感染対策・災害対策
コロナ禍の経験を生かした感染対策と
地震と水害を重視した災害対策
患者の安全性を確保するために感染対策や災害対策にも注力している。「感染対策はコロナ禍での経験を踏まえ、正面玄関の東側に別玄関を設け、一般患者さんと感染が疑われる患者さんとの動線を区別しました」と田中統括マネジャー。感染者は専用の玄関から専用診察室、トイレ、専用個室に直接行くことができる。また、専用診察室の手前には、スタッフがガウンや手袋などの防護具を着脱する脱衣室も設けた。
透析室の個室は1床しかないため、感染症流行に備え、透析室には可動式のガラス戸パーテーションを設置している。「感染者が増えて個室対応ができなくなったとき、このパーテーションで仕切ることで透析室の奥に最大6名の感染者が収容できる隔離室を作ることができます」と松田マネジャーは説明する。また、普段から空気が一方向に流れるように空調設備を設定しておくことで、細菌やウイルスなどが室内に拡散しない工夫も行っている。
さらに災害対策で強化したのは地震対策と水害対策だ。「グループ病院より地震対策を強化し、機械室の各種機器には免震装置を取り付けています。また、クリニックの建設地は比較的低地のため、水害リスクも重視しました。正面玄関は止水板を装着できる造りになっています」(武智副主任)。

透析室に設けられた可動式のガラス戸パーテーション。これで仕切れば最大6人の感染者が収容できる隔離室になる


感染者専用の玄関から専用診察室、トイレ、専用個室に直接行くことができる(左写真)。専用診察室の手前には防護具の脱衣室も設けた

専用個室

機械室も地震対策を強化し、水処理装置をはじめ各種機器には免震装置を設置している

水害対策にも注力し、正面玄関は止水板を装着できる仕様に
5. 展望と課題
法人リソース、福祉サービスを活用しながら
患者が安心して透析ライフを楽しめる環境を
当面の目標について、松原院長は増患を挙げる。「グループ病院との差別化を図るうえでも早朝透析の患者数を特に伸ばしていきたい」と意欲的だ。同時に患者の「エンジョイ 透析ライフ」を充実させるために法人リソースの活用にも注目している。
「法人が運営する健康増進施設『はあもにい倉敷』では、フィットネス系プログラム(ストレッチ、マシーントレーニング、ヨガ、太極拳、合気道、バレエ、フラダンス、ブレイクダンス、ピラティス、ノルディック・ウォーク、吹き矢など)から文化・教養系プログラム(俳句、短歌、語学、書道、中国茶、音楽、絵画など)まで幅広く取り揃え、さまざまな講座を受講することが可能です。このようなリソースをうまく活用しながら、患者さんに生活の楽しみや生きがいを持ってもらえるような支援も行っていけるのが理想です」と松原院長は話す。
また、「血液透析患者数の減少傾向を踏まえ、今後は腹膜透析にも積極的に取り組む必要があります」と指摘する。「患者さんのニーズや状況・環境にいち早く対応し、それに応じて腹膜透析の方向にシフトすることも非常に大事になってくると感じています」(松原院長)。
高齢の透析患者の増加が予測される中、松田マネジャーは地域包括支援センターや福祉サービス事業者との連携強化を課題に挙げる。「私たちは患者さんの生活を支えていかなければなりません。5年以内には自分で運転して通院できる患者さんが減り、介護保険の介護タクシーを使って通院する患者さんが増えてくることを考えると、今から連携を強化していくことが求められています」(松田マネジャー)。
法人の実証実験の場として同クリニックを活用していきたい展望もある。「働きやすさを重視する当クリニックでは、スタッフが自由に意見を言える環境が整っています。そして、よい意見をどんどん取り入れて、新しいことにチャレンジする風土が醸成されつつあります。こうした強みを生かし、いろいろなことに率先して取り組み、データをしっかり取ったうえで効果のある方法や活動をグループ病院に広げていく。そのような役割が担えるのではないかと考えています」と田中統括マネジャーと武智副主任は口をそろえる。
患者がいきいきとした透析ライフを満喫できるよう、チーム一丸となって"攻めの透析"を展開するしげい腎クリニック早島。その挑戦は現在進行形で続いている。

松原院長を囲んで。法人内の各施設から抜擢されたスタッフの皆さんは、全員病院勤務の経験と10年以上のキャリアを持つ
KKC-2025-00799-1
透析施設最前線
-
2026年1月8日公開/2026年1月作成
-
2025年12月17日公開/2025年12月作成
-
2025年11月4日公開/2025年11月作成
-
2025年10月20日公開/2025年10月作成
-
2025年9月25日公開/2025年9月作成
-
2025年9月16日公開/2025年9月作成
-
2025年8月27日公開/2025年8月作成
-
2025年7月17日公開/2025年7月作成
-
2025年4月14日公開/2025年4月作成
-
2025年4月2日公開/2025年4月作成
-
2025年3月10日公開/2025年3月作成
-
2024年10月15日公開/2024年10月作成
-
2024年9月17日公開/2024年9月作成
-
2024年3月7日公開/2024年3月作成
-
2024年2月2日公開/2024年2月作成