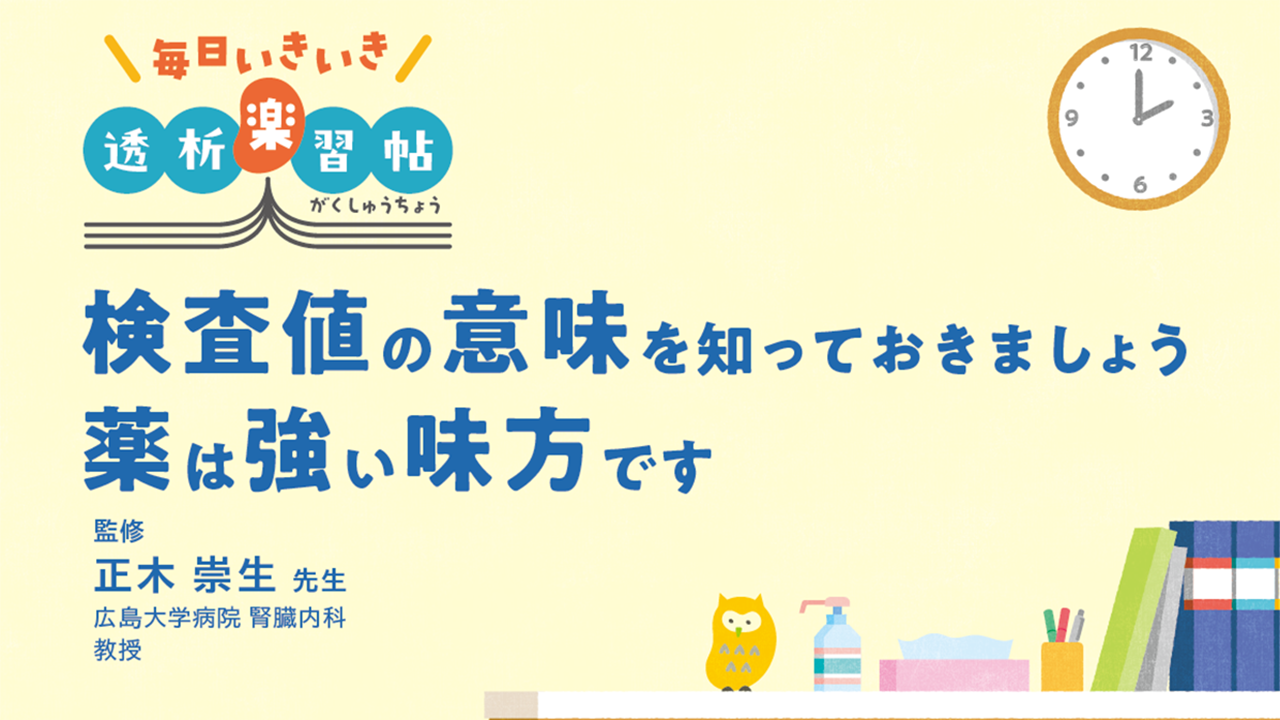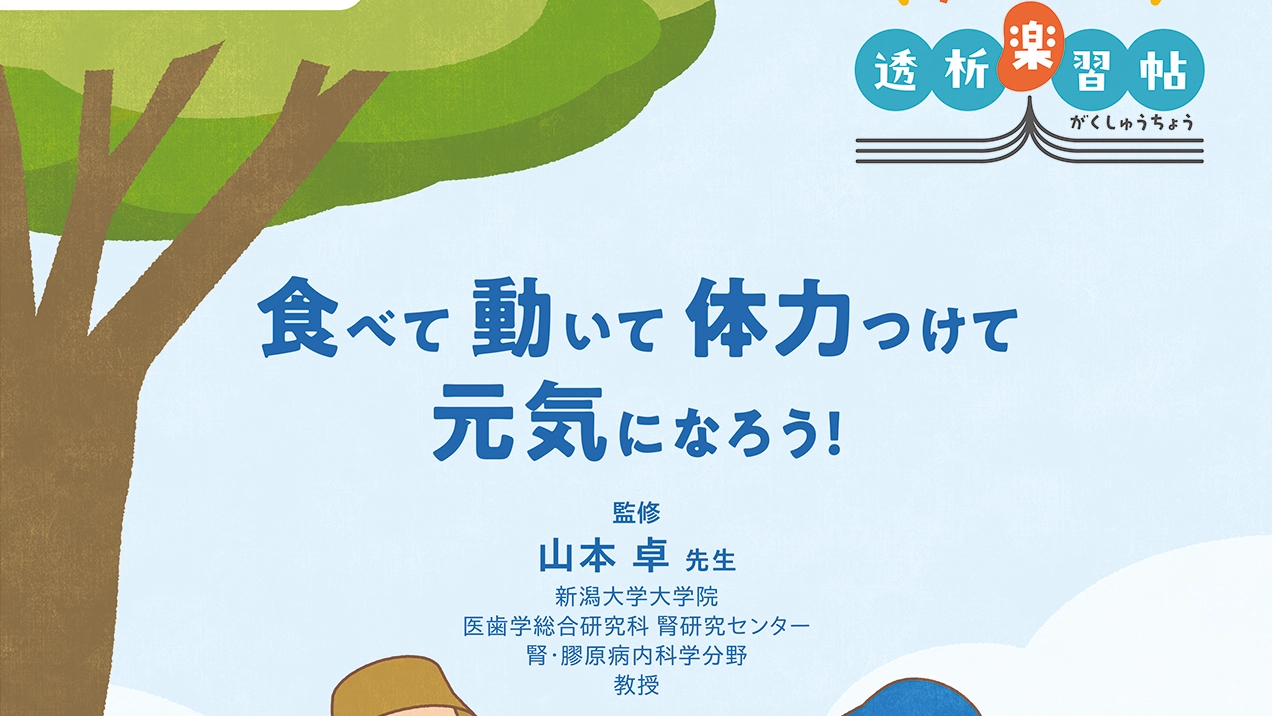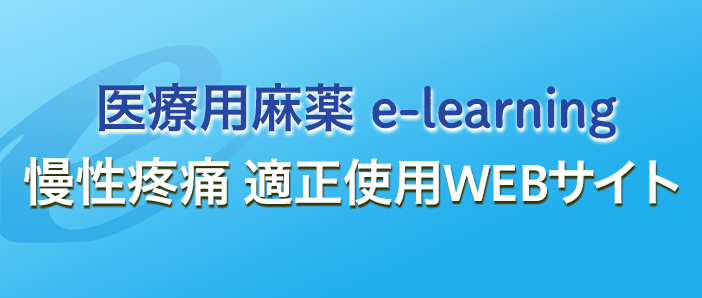社会医療法人若竹会 つくばセントラル病院
[透析施設最前線]
2025年4月2日公開/2025年4月作成

- ●理事長:金子 洋子 先生
- ●院長:金子 剛 先生
- ●開設:1988年12月
- ●所在地:茨城県牛久市柏田町1589-3
「一人の人を大切に」の理念が息づく地域中核病院
透析患者にも医療・介護・福祉を包括的に提供
つくばセントラル病院は茨城県を拠点に、病院、介護医療院、クリニック、介護施設、各種在宅ケア関連事業所など多様な展開を行い、それぞれの連携によって医療・介護・福祉サービスを包括的に提供している『わかたけヘルスケアシステム』の中心的な機関である。腎臓病に関しても、保存期管理から透析導入、外来透析、入院透析、腎臓リハビリテーション、合併症治療、終末期ケアまでトータルに提供し地域の患者を支えている。その活動の根底には「一人の人を大切にする」という創設時からの理念が息づいている。
1. 法人の概要と特徴
スーパーケアミックス病院を中心に
地域の多様なニーズに応える

金子 洋子 理事長
1988年12月、当時、筑波大学附属病院に勤務していた竹島徹・現社会医療法人若竹会会長が、大学病院での治療を終えた患者を受け入れる良質な病院をつくるべく、つくばセントラル病院(当時128床)を開設した。「土地探しも資金集めも、一から始めたと聞いています。以来、施設や設備、機能を少しずつ拡充し、現在までに313床の総合病院に成長しています」と話すのは、2023年10月、父である竹島会長から法人の経営を引き継いだ金子洋子理事長だ。
「開業からほどなくして、これからの時代は"治し支える医療"が必要だと気づいた竹島会長は、1997年には、病院に隣接して介護老人保健施設セントラルゆうあいを開設。その後は、医療・介護・福祉サービスを包括的に提供する体制づくりを進めてきました」と続ける。
組織的には、2013年に茨城県内で2番目に認可された社会医療法人若竹会と2000年に設立した社会福祉法人若竹会を、一般社団法人わかたけヘルスケアシステムが束ねるかたちとなっている。わかたけヘルスケアシステムの代表理事も金子理事長が務め、グループ全体の統率をとっている。
つくばセントラル病院は若竹会の原点でありいまも中心的な存在だ。2018年には地域医療支援病院に、2019年には災害拠点病院に指定されるなど、地域においても中核的な役割を果たしている。313床の内訳は、DPC病床195床、緩和ケア病床20床、回復期リハビリテーション病床55床、HCU8床、地域包括ケア病床35床。介護施設や行政とも連携しながら、いわゆるスーパーケアミックス病院として地域の多様なニーズに応えている。
医師数は常勤77名、非常勤145名。病院は開業時に建てたA棟、2000年以降に順次竣工したB棟、C棟、D棟の4棟からなり、別館として建つ高精度放射線治療センターには、定位放射線治療装置や最新の高精度放射線治療装置などを配備している。一部の専門的な治療については筑波大学附属病院をはじめとした近隣の高度医療施設に依頼するなど連携体制も万全だ。2024年6月には、これら近隣の医療機関の院長などを招いて行っていた「地域連携懇談会」を、理事長交代の挨拶も兼ねて復活し、協力関係を一層発展させていくことを確認した。
一日平均外来患者数は2023年度実績で851人と、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行が始まった2020年度を除いてほぼ右肩上がりに増加している。産科に力を入れていることでも知られ、2023年度実績で分娩数415件と、牛久市内の出生数418に並ぶ数を誇る。災害拠点病院としては、令和6年能登半島地震に際して1月中に2回、DMATを派遣した。
若竹会グループの病院にはつくばセントラル病院のほかに、牛久市の北側に隣接する土浦市に2022年11月に開院した土浦リハビリテーション病院 介護医療院(回復期リハビリテーション病床34床、地域包括ケア病床8床、介護医療院96床)がある。また、茨城県内だけで、2つのクリニック、10の介護施設、3つの在宅医療・介護関連施設を持つ。グループ全体で医療355床、介護835床、合計1190床のベッドを擁し多くの患者を受け入れている。グループの活動のベースにあるのは、竹島会長から引き継がれている理念、「一人の人を大切にする慈愛の医療と福祉の活動に徹する」である。
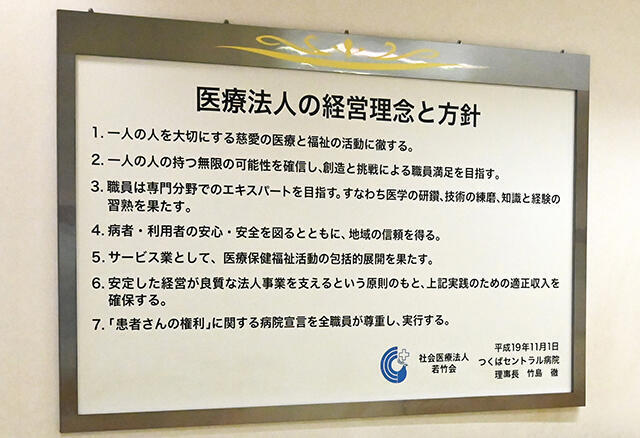
創業時からの理念が院内随所に掲示され職員間で共有されている
2. 透析医療の取り組み
3つの透析施設で透析装置176台が稼働
患者の送迎サービスは開業時から継続
若竹会の中で透析施設を持っているのは、つくばセントラル病院、土浦市にある土浦リハビリテーション病院 介護医療院、牛久市の南側の龍ケ崎市にあるセントラル腎クリニック龍ケ崎で、透析装置は3施設合計で176台。外来透析患者数は同じく合計で約380人(平均/日)。2つの病院では入院透析にも対応している。ここ数年の透析実績(3施設合計、外来・入院含む)は、月平均の延べ回数換算にして5,000件前後でコロナ禍でも大きな変化なく推移している。どの施設も非常用発電装置や湧水処理システムなど災害対策も整っている。
年1回の腹部エコー、心エコー、ABI検査、骨密度検査、半年ごとの感染症チェック、月に1度の心電図検査、X線検査、フットケア、月2回の血液検査など合併症予防の取り組みは3施設共通。問題が見つかればつくばセントラル病院で速やかに治療介入する。管理栄養士による栄養指導および生活指導や服薬指導なども含めた広い意味での腎臓リハビリテーションにも3施設共通して取り組んでいる。さらに、手技の統一化、資材の統一化などをこれまで以上に推進するため、合同の研修などにも力を注ぐ。
また、透析患者の送迎サービスを1988年の開設時から行っており、一般車両と車椅子専用車両を複数台、エリアごとにコースを設定して走らせている。3施設それぞれの特徴を以下に記す。
■つくばセントラル病院
つくばセントラル病院では、C棟2階の広々したフロアを腎センターとして活用している。透析装置は81台。開設時は7台だったということからもその成長ぶりが伺える。81台のうち7台は個人用透析装置、1台は多目的血液浄化装置である。一般的な装置のほかにこうした機器を比較的多めに配備している理由について、3つの透析施設の臨床工学部門を統括している臨床工学部の中山裕一部長(兼技師長/医療DX推進室室長)は、「患者さんそれぞれの病状や病態に合わせた処方透析に的確に対応することが第一の目的です」と話す。
コロナ禍をきっかけに感染対策も進め、個人用多用途透析装置・個人用透析用水作製装置を最大4台備えた隔離透析室を増設し、カーテンによるゾーン分けの仕組みも整えた。「COVID-19が2023年5月に5類感染症に移行するまでの約3年間に陽性となった透析患者さん87名の透析を実施しました。当院は新型コロナウイルス感染症重点医療機関に指定されていたこともあり、他の施設の透析患者さんも積極的に受け入れました」と中山部長。規模だけでなく、機能面でも地域で中核的役割を果たしている透析施設といえる。
つくばセントラル病院の透析実績は、直近の2023年の年間回数ベースで3万1,620回(うち11.6%が入院透析)となっている。スタッフ数は、医師が常勤7名、非常勤10名、看護師23名、臨床工学技士24名、ナースエイド(看護助手)7名、クラーク3名。透析スケジュールは、月曜から土曜まで、昼、夜間の2クールを実施し、夜間は22:00まで対応することで患者の社会復帰を後押ししている。
2024年4月には、透析中の患者と近隣の薬局の薬剤師をオンラインでつなぎ、透析を受けながら服薬指導を受けてもらう取り組みを開始した。患者のアドヒアランスの向上、腎センタースタッフの負担軽減など良い効果が出始めているという。

中山 裕一 臨床工学部長兼技師長/医療DX推進室室長


広いフロアに81台の透析装置を配したつくばセントラル病院腎センター。広いフロアもカーテンによって仕切ることができる

コロナ禍に新たに陰圧装置を設置した隔離透析室


ポータブルエコー装置、ハンディエコー装置を複数備え、エコー下穿刺などで活用

パソコンを使った薬局薬剤師によるオンライン服薬指導。機器の 準備など透析室での作業は薬局のクラークが行う


機械室には空気中の低濃度粒子を捕集できるHEPAフィルターを備えたクリーンブースを備えている。水処理システムは故障時などに 備えバイパスでつながる2系統を完備

地下水濾過システム。湧水を基本に必要に応じて水道水も使える ようになっている
■セントラル腎クリニック龍ケ崎
セントラル腎クリニック龍ケ崎は2008年9月に開設された。当初は透析装置56台でスタートしたが、ニーズに合わせて増床し、現在は65台が稼働している。このうち3台は個人透析装置であり、透析室内には、主に感染症対応としての個室が1部屋完備されている。外来透析のみ実施しており、透析患者は約170人。2023年の年間透析回数は2万4,540回となっている。
龍ケ崎市内には、同クリニックのほかに透析施設が1つしかなく、規模も11床である。そのため龍ケ崎市在住の透析患者の大半が同クリニックを利用している。透析スケジュールは月・水・金が昼、夜間の2クール、火・木・土が昼のみ1クールである。夜間透析は20:30までだが、もっと遅い時間を希望する患者にはつくばセントラル病院を利用してもらうことができる。
山口直人院長は同クリニックについて、「維持透析対応のクリニックですが、腎臓内科や透析関連の専門家だけでなく心臓血管外科、循環器科、血液内科、総合内科などの専門医も関わって、多職種が協力し合い、患者さんが長年の間に身につけてきた生活習慣や価値観を考慮した指導や治療を行っています。何かあればすぐにつくばセントラル病院で検査・治療を受けていただくことができるので、安心して通院いただけます。同じグループの高機能の中核施設が近くにあるということは、私たち医師にとってとても心強いものです」と話す。
山口院長は水戸済生会総合病院腎臓内科・内科部長、茨城県立医療大学保健医療学部教授などを歴任した経験から県内の医療事情にくわしく、その立場からも若竹会グループの機能や体制を高く評価している。
同クリニックのスタッフの1日は、8:00のミーティングから始まる。その時間にはすでに送迎車が地域を回っており、ミーティング中に運転手から連絡が入ることもしばしばだ。「たとえばある患者さんが家から出てこないといった連絡があった場合、私たちはご家族にお電話したり、場合によっては看護師がご自宅を訪ねて状況を確認したりもします。こうした対応をしながら透析の準備を進め、いらっしゃる患者さんを次々にトリアージして、この時点で顔色が悪い、反応が鈍いといったことがあれば早急に治療介入します」と山口院長が現場の様子を紹介する。

(写真提供:つくばセントラル病院)

山口 直人 セントラル腎クリニック龍ケ崎院長
■土浦リハビリテーション病院 介護医療院
土浦リハビリテーション病院 介護医療院腎センターの透析装置は30台。2022年、コロナ禍という特殊な環境下での開設だったこともあり、最初から陰圧装置のついた個室を2部屋完備している。回復期リハビリや介護医療院といった病床の特性とも関連し、患者には高齢者が多く、入院透析の比率が高いことも特徴である。そのため個人透析装置を2台備えて処方透析に的確に対応している。透析は昼のみで、生活指導やフットケアにも力を入れている。
2024年4月に歯科口腔外科が開設されたことは、同院の診療の質を大きくアップさせている。「高齢者の誤嚥性肺炎の問題が指摘され始めて久しい中、高齢患者さんへの歯科診療の重要性はますます増しています。透析患者さんにも口腔の問題を持つ人は多く、今後は腎センターと歯科口腔外科との連携も深めていきたいと思っています」と金子理事長が言う。
龍ケ崎市とは反対に、土浦市は透析施設の激戦区だというが、比較的市街地に近く通いやすい立地であること、入院できること、何かあった時にはつくばセントラル病院での治療も速やかに行えることなど利点が多いため、今後は利用者の増加が見込まれている。

(写真提供:つくばセントラル病院)
3. 院内救急システム
病院独自の高規格救急車で
患者を速やかに最適な医療につなぐ
つくばセントラル病院は救急医療にも力を入れている。救命救急士が同乗する同院独自の高規格救急車(以下、病院救急車)を2台擁し、かかりつけ患者の自宅や施設からつくばセントラル病院へ、同院から他の医療機関へといった患者の搬送を行う「フレンズ」と名付けられた仕組みを持ち、あらかじめ登録された患者を中心にサービスを提供している。
病院救急車と救急救命士(男性11名、女性4名)は同院の救急総合診療センターに所属している。救急救命士は日勤5〜6名、夜勤2名のシフト制をしき、24時間365日体制で出動要請に応える。グループ内での移送の場合は電子カルテを共有しているので、搬送後の対応は非常にスムーズだという。
フレンズも含めたつくばセントラル病院の救急車受け入れ台数は2023年度実績で4,332台。2015年度が2,005台だったことを考えるとわずか8年で2倍以上に増えていることになる。「フレンズ」は、患者を速やかに適切な医療につなぐことはもちろん、消防署救急車の出動回数の軽減にも貢献している。
救急総合診療センターでは、救急車の出入り、待機がより安全に行えるよう、出入り口に大きなひさしを設けている。ひさし下のスペースは透析患者用の送迎車も利用しており、悪天候時にも快適に通院できるようになっている。

高規格の病院救急車を2台擁し患者の速やかな搬送に貢献している

大きなひさしを設けた救急総合診療センター出入口。透析患者の 送迎もここを起点とするため雨を避けることができる
4. 人材育成
全員参加の院内業績発表会を毎年実施
多職種がお互いを高め合い交流を深める
わかたけヘルスケアシステムの総職員数は、2024年6月現在1,922名(常勤換算1,640.2名)を数える。人材育成は職種ごと、部門ごとのほかにグループをあげた取り組みも実施している。その代表的なものが毎年実施されている「医療・介護業績発表会」である。牛久市内の生涯学習センター大ホールを借り切って行われる院内発表会は、職員全員参加が原則だ。「開院当初から絶えることなく続いている会で、2023年で第34回を迎えました。新人にとっては登竜門であり、公式な学会発表などにつなげる場でもあります。医療・介護・福祉のスタッフが一緒になってセミナー形式で学んだり、多職種が交流したりとスキルアップとコミュニケーションの場にもなっています」と金子理事長が紹介する。たとえば臨床工学部では関連学会で毎年10演題ほどの発表を行っているが、その土台となっているのがこの発表会だと中山部長は言う。
2023年の院内業績発表会では56演題が発表されたが、その中には、クロイツフェルト・ヤコブ病の透析患者を受け入れた際の感染対策についての発表があった。このテーマで後に、看護師が日本透析医学会学術集会で、中山部長は危機管理をテーマに日本臨床工学会で発表している。
また、発表内容を院内のマニュアル改訂につなげた例もある。透析用のカテーテルの管理方法に関する研究で、感染や閉塞を少なくすることが目的だった。まずは医師、看護師、臨床工学技士がグループをつくって先進施設を見学。ここで学んだ内容を、従来からあった院内のマニュアルに盛り込んだ。いまでは3施設合同で活用しているこのマニュアルには、透析開始前のポンピングや清拭の方法などが記されており、成果を上げている。
「臨床データを取りたいときに医師に相談すると快く協力していただけます。そういう意味で当法人は、各職種が研究をしやすい良い環境にあると思います」と中山部長。金子理事長も、「医師が協力することで看護師などの発表内容が良いものになります。良い発表ができると、次も頑張ろうと思ってもらえますので、医師の協力は大事だと感じています」と言う。優秀演題賞の表彰など評価の仕組みもあり、職員のモチベーションにつながっている。
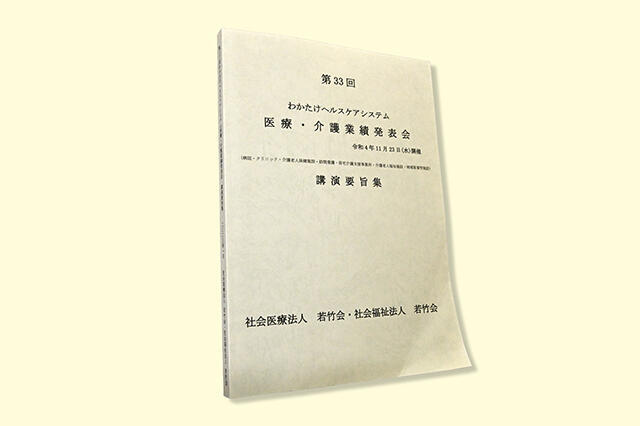
院内業績発表会の発表内容をまとめた冊子は学会さながらだ
5. 今後の課題・展望
「一人の人を大切にする」を愚直に守りつつ
DX推進により時代に合った病院づくり
医療・介護・福祉の未来を見据えながら理事長主導で進めている取り組みとしてはDX(Digital Transformation)の推進がある。すでに、健診センターなどでは、自分の診療情報や健康診断の結果を画像データも含めて閲覧できるオンラインサービス「カルテコ」を導入済みだが、今後はこれを透析施設にも広げていく方針だ。「透析条件などを自由に閲覧できるようにしておけば、災害時などにとても便利だと思います。透析通信システムとどのように連動させるか、調整を進めているところです」と中山部長。実現すれば、現在、「災害手帳」として患者が紙ベースで持っているものがスマホで携帯できるうえ、透析条件の更新も簡単にできるなど施設側にとっても患者側にとっても有益だ。
また、コマンドセンターによる病床管理の仕組みの構築も進めている。電子カルテ上のデータを自動的に分析・可視化し、ケア需要の予測、施設間の移動などを的確に把握。患者の重症度に合わせてどの病床が適切かなど、提案機能も活用しながら、質の高い医療・ケアをタイムリーに提供しつつ、病床の稼働率を上げていくことを目指している。
金子理事長は、新理事長としての抱負を次のように語る。 「開業から35年。当法人がここまで発展してこられたのも、一人の人を大切にする、病院は地域のものであるという考え方のもと、職員が一致団結して努力を重ねてきたからだと思います。この姿勢を私も踏襲し、地域に貢献していきたいと思います」
「治し支える医療」「DX」「地域連携」「栄養」を「未来プロジェクト」の4つの柱として掲げ、法人の新たな取り組みを先頭に立って進めている金子理事長。直近では、病院給食や介護療養食を施設ごとにつくる体制を見直し、2024年6月、法人グループ内の食事を一括製造する「セントラルキッチンわかたけ」を設立した。材料費の高騰、人材不足など課題が山積する中でも高齢患者への栄養の充実を実現するのが目的だ。このように、できることを一つひとつ積み重ねながら、新しい時代に合った病院づくりに邁進している。
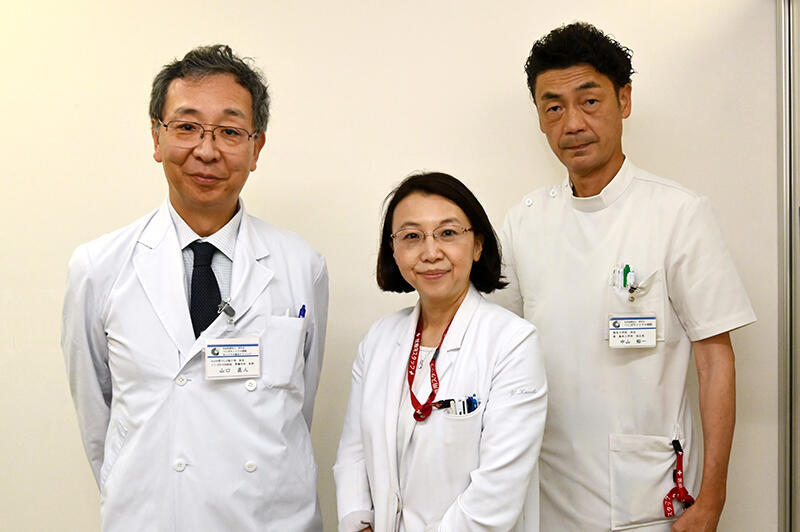
金子理事長を囲んで
KKC-2025-00163-1
透析施設最前線
-
2026年2月16日公開/2026年2月作成
-
2026年1月8日公開/2026年1月作成
-
2025年12月17日公開/2025年12月作成
-
2025年11月4日公開/2025年11月作成
-
2025年10月20日公開/2025年10月作成
-
2025年9月25日公開/2025年9月作成
-
2025年9月16日公開/2025年9月作成
-
2025年8月27日公開/2025年8月作成
-
2025年7月17日公開/2025年7月作成
-
2025年4月14日公開/2025年4月作成
-
2025年4月2日公開/2025年4月作成
-
2025年3月10日公開/2025年3月作成
-
2024年10月15日公開/2024年10月作成
-
2024年9月17日公開/2024年9月作成
おすすめ情報
-

会員専用コンテンツの一部をご紹介します。 -

ダーブロック錠特設ページ -

CKD領域において地域医療連携に積極的に取り組む医師へのインタビュー、施設紹介、診療技術・スキルの解説、クリニカルパスなどを紹介しています。 -
{{list.title}}
-
おすすめ情報は、協和キリンのウェブサイトにおける個人情報の取扱い方針に基づき、お客様が閲覧したページのアクセス情報を取得し、一定の条件に基づき自動的に表示しています。
そのため、現在ご覧いただいているページの情報との関連性を示唆するものではございません。